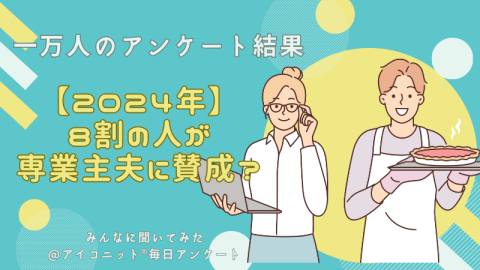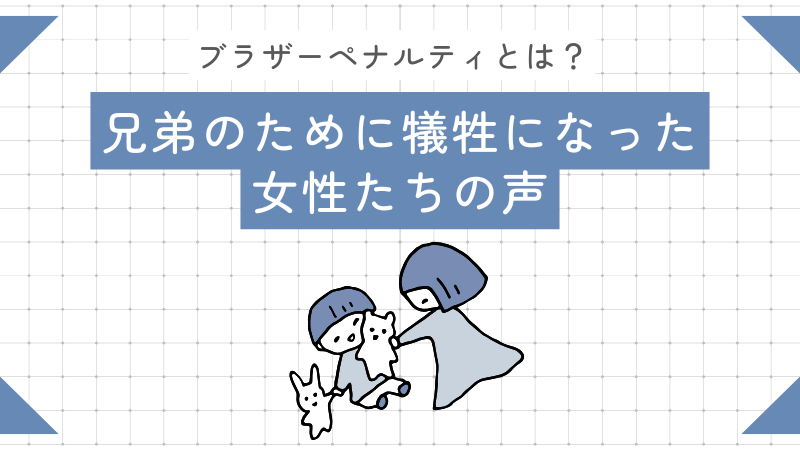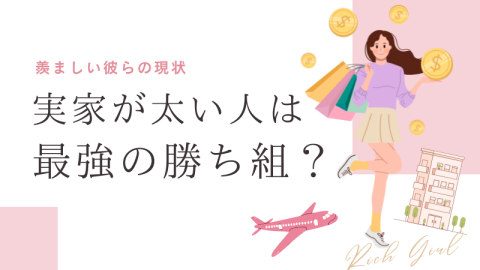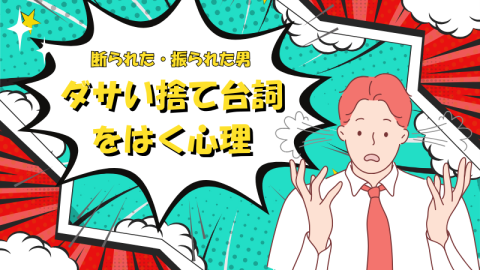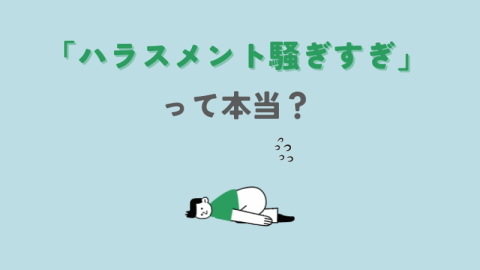近年、SNSやネット上で最近注目を集めている「ブラザーペナルティ」という言葉をご存知でしょうか。
ブラザーペナルティとは、兄や弟がいることで女性に課せられるペナルティのことです。
なぜか自分だけが我慢を強いられる、期待される役割が重くなる、進路や人生の選択肢が狭められる……近年、そんな経験をした女性たちが、自分の体験に名前をつけることで、長年抱えてきたモヤモヤに向き合い始めています。
本記事では、ブラザーペナルティとは何か、なぜ生まれるのか、そしてその影響を受けた女性たちがどのように自分の心と向き合えばよいのかについて、深く掘り下げていきます。
「なぜか兄だけ贔屓されてきた」「兄や弟がいることで我慢を強いられてきた」という経験がある方や、ブラザーペナルティについて知りたい方は、本記事をぜひ参考にしてみてください。
ブラザーペナルティとは?

ブラザーペナルティとは、家庭内に男性の兄弟がいることによって女性が受ける不利益や制約を指す言葉です。具体的には、以下のような状況が挙げられます。
- 家事や介護の責任を女性が負わされる
- 大学進学や進路選択で男性が優先される
- 女性らしさを強要され、自由な行動が制限される
ブラザーペナルティという言葉はいつから使用されている?

ブラザーペナルティは、海外の研究でも「Brother Effect」や「Sibling Gender Effect」と名付けられ、認識されてきました。
特にX(旧Twitter)やTikTokなどで「#ブラザーペナルティ」のハッシュタグとともに体験談が共有され始め、多くの女性が「自分だけじゃなかった」という気づきを得ているのが現状です。
ブラザーペナルティという言葉が注目され始めた背景

ブラザーペナルティは昔から存在しました。昔は男子が女子よりも優遇されるのが当たり前で、男子には女子よりも一品多いおかずが配分されることもあったほどです。
現在はそこまであからさまな女性差別は少ないものの、女子にだけ家事や介護を押し付ける風潮や、男子ならば浪人してもOKだが女子は許されないなど、女子だけに無償労働を押し付け、教育機会を損なわせる扱いは連綿と続いています。
そういった不平等をブラザーペナルティという言葉で表すことができるようになった背景には、ジェンダー平等意識の高まりが挙げられるでしょう。
また、女性が外で働くようになったこともブラザーペナルティという言葉が注目され始めた一因です。女性は家事育児、男性は会社、とはっきりと性別役割が分かれていた時代であれば、女性だけ高等教育を受けられなかったり、無償労働の責任を負わされたりしても、「それが女性の役割だから」と考えざるを得ませんでした。
しかし、1980年代には共働き世帯が専業主婦世帯の数を上回り、以降、外でも家庭内でも働かなくてはならない女性の割合が増加し続けています。また、統計上、「男性が外で働いている時間<女性が外で働いている時間+家事や育児の時間」であることも判明しています。
このように、女性の社会進出が進んでいるにも関わらず、相変わらず家事・育児・介護の負担が女性に偏っていることから、女性たちはブラザーペナルティの理不尽さを実感し、SNSなどで体験を共有するようになったのです。
なぜブラザーペナルティが生まれるの?
次に なぜブラザーペナルティが生まれるのか、について見ていきましょう。
伝統的な家族観とジェンダー役割意識がブラザーペナルティの根本的な原因
ブラザーペナルティが生まれる根本的な原因は、長い間日本社会に根ざしてきた伝統的な家族観とジェンダー役割にあります。
日本の伝統的な家制度では、男性が家系を継ぎ、女性は嫁いで他家に入るという考え方がありました。この考え方により、男性は将来の家長として大切に育てられ、女性は「いずれ嫁ぐ身」として扱われることになったのです。
また、性別によって期待されるものが違うことも関係しています。
男性は学歴やキャリア、経済力を求められる一方、女性は協調性やケア能力、家事能力を求められがちです。この違いが、教育機会の格差や、家庭内で女性にだけ家事という無償労働を押し付ける流れを生み出しているのです。
無意識のバイアスとマイクロアグレッションもブラザーペナルティにつながる
多くの場合、親は意識的に差別しているわけではありません。しかし、社会に根ざした無意識のバイアスが、日常的な小さな差別(マイクロアグレッション)として現れます。
例えば、親が子供に「女の子なんだから、家事くらいできないと」という理由で妹だけに家事をさせ、兄は家事をすることを期待されない場合もあります。この場合、親は、娘を差別しようと思っているわけではないでしょう。
実際、家事などのケア労働ができる女性は、「女子力が高い」「女らしい」と高い評価を受けがちなため、親は「良かれと思って」娘にケア労働をさせようとしているのかもしれません。
娘にだけ家事をさせるという行動は、娘にだけ労働を強いるという意味で、女性差別に他なりませんが、親は悪気なく行っているケースが少なくないのです。
経済的事情と統計的差別もブラザーペナルティの原因
限られた家計の中で、教育費や将来への投資を男性に集中させる家庭も少なくありません。
これは経済的合理性(日本は男女の賃金格差が大きいため、男児に投資した方がより多くのリターンが期待できる)として正当化されがちですが、結果として女性の機会を奪うことになります。
こういった「統計上、男性の方が稼げるから男性に投資するのは当然」といった行動のことを統計的差別と呼びます。
兄や弟の存在が「女性」に与える影響とは?

兄や弟は女性にさまざまな影響を与えます。
長女への影響:「お姉ちゃんなんだから」の重圧
ブラザーペナルティを受けやすい属性として、「長女」が挙げられます。
また、教育費を弟に優先的に使われる、習い事や進路選択で弟が優先される、将来性への投資で格差をつけられる、となどの実害を被るケースもあります。
実際の声
「私は勉強ができたのに、『女の子は大学に行かなくても』と言われ、弟の大学費用のために私は短大進学になった。弟は成績が悪かったのに、私立大学に行かせてもらった」(30代女性)
「片親家庭で親が不在なことも多かった。小さい頃から私が家事や弟の世話をしていた。今振り返ってみると、なんで子供なのに親の役割を担わされていたんだろうと理不尽に感じる」(20代女性)
妹への影響:保護という名の制限
妹の場合は、「可愛がられる」反面、過保護という形でのペナルティを受けることがあります。
実際の声
「お兄ちゃんは留学や東京の大学への進学を許された。それなのに私は、家から離れることが許されなかった。その結果、希望の大学に進学できなかった」(40代女性)
なぜ日本ではブラザーペナルティの影響が強いとされるのか

日本は、ブラザーペナルティが発生しやすいと言われています。
家制度の名残があり、男尊女卑が続いている
現代の日本は、家制度の名残があり、いまだに女性差別が行われています。
また、現状、国を挙げて男女平等を目指すつもりがないことは、性差別を是正するための部署に男女共同参画という奇妙な単語が使われていることからも明らかです。
なぜ、男女平等や男女同権というこれまで使われていた言葉を使わず、男女共同参画という新たな言葉を生み出したのかというと、男女同権あるいは男女平等という言葉に反発を覚える人が、国の中枢に多く存在しているからでしょう。
続く男性稼ぎ主モデル。女性が稼ぎにくい経済構造

また、日本の雇用制度や経済構造も、ブラザーペナルティを後押ししています。
日本は長らく、男性の長期雇用・年功序列制度を採用してきました。男性が会社で働き、会社は男性が妻子を養えるだけの賃金を支払う構造を男性稼ぎ主モデルと言います。
男女雇用機会均等法ができて以降、女性の雇用が拡大され、女性の社会進出は進んだと言われがちです。しかし、女性が男性と同様に働けるようになったわけではありません。なぜなら、男女雇用機会均等法ができたと同時に、総合職・一般職、という区別が生まれたからです。この区別は、海外ではほぼ見られません。
一般職は総合職より給与が低く抑えられています。つまり、総合職・一般職という縛りは、女性をより低賃金な職にとどめておく効果を発揮しているのです。
このようなシステムでは、女性はいくら教育を受けても高収入は得られないことになります。実際、統計上、女性の大卒の平均的な収入は、男性の中卒以下です。
つまり現状日本においては、教育費に対する投資回収率が男性の方が高くなるのは明らかなわけです。こういった統計的な事実に基づいて、ブラザーペナルティが発生するケースもあります。
メディアが性別役割を強化している
メディアやコンテンツも、性別役割分担を強化する要因となっています。
女性の自己犠牲を美徳化したり、若い女性アナウンサーを高齢男性MCのサポート役として配置し続けたりすることで、「男性や子供をサポートし、ケアする女性こそ素晴らしい」「自我を殺して、他人のために生きる女性こそ賢くて美しい」というメッセージを社会に浸透させています。
同調圧力
日本社会特有の同調圧力も、ブラザーペナルティを維持する要因です。
ブラザーペナルティの具体的影響

次に、ブラザーペナルティが課せられたことにより、発生しうる影響について確認しましょう。
教育機会への影響
- 希望の進学が許されない
- 留学が許されない
キャリア形成への影響
- 就職活動での家族の支援が受けられない
- 起業や独立への支援が受けられない
- 教育投資が十分受けられなかったため、キャリア形成がうまくいかず、低賃金労働を余儀なくされる(年収が低い)
人間関係と心理的影響
- 自分の価値が信じられず、自らを軽視するようになる
- 自分の能力や才能が信じられず、自信が持てない
- 親から愛されていると感じられず、恋人との関係にも影響が出る
- 将来への不安が強く、挑戦する前に諦めてしまう
- 男性が優遇される環境に慣れきっているため、女性差別的な男性に惹かれる
- 自分を対等に扱う男性との関係に居心地の悪さを感じ、逃げ出したくなる
老後の影響
- 介護の責任を負わされ、離職を余儀なくされる
- 経済的自立が困難になる
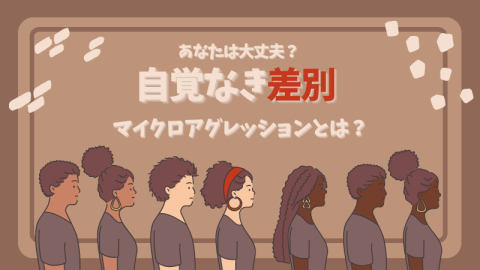
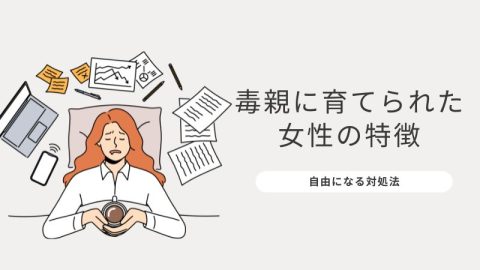
ブラザーペナルティの被害に遭ってしまったら?対処法を解説

最後に、ブラザーペナルティの被害にあった女性が、どのように対処していけばいいのか、について確認しましょう。
体験を言語化する
まずは自分が経験したことを客観的に見つめ直すことから始めましょう。
【具体例】
- 具体的な出来事を書き出してみる
- その時の感情を振り返る
- 家族の行動パターンを分析する
怒りを認める・あるがままに見る
自分の感情を否定せず、正当な怒りや悲しみを認めることも重要です。
【具体例】
- 「自分が悪かったのかも」という自己否定をやめる
- 理不尽な扱いを受けたことを認める
- 被害者としての自分を受け入れる
境界線を設定する
成人後も家族から不公平な扱いを受けている場合には、明確な境界線を設定することが必要です。
【具体例】
- 過度な期待や要求を断る勇気を持つ
- 兄弟との比較を拒否する
- 自分の人生の優先順位を明確にする
セルフケアを重視する
長年の影響で傷ついた自己肯定感を回復するには時間がかかります。じっくり心の傷と向き合い、必要であれば専門家のサポートを受けましょう。
【具体例】
- 自分の成功や成長を認める習慣をつける
- 他者との比較ではなく、過去の自分との比較を意識する
- 小さな目標を達成する体験を積み重ねる
- カウンセリングやセラピーを活用する
- 同じ体験を持つ人とのグループ活動に参加する
- 自助グループやオンラインコミュニティに参加する
価値観を見直す
家族から植え付けられた価値観ではなく、自分自身の価値観を見つけることも重要です。
【具体例】
- 本当にやりたいことを探求する
- キャリアや人生設計を自分で決める
- 結婚や家族のあり方を自分で選択する
次世代に引き継がない
自分が親になった場合、同じ過ちを繰り返さないことも重要です。
【具体例】
- 性別による期待や制限をかけない
- 子ども一人ひとりの個性を尊重する


さいごに。次世代にブラザーペナルティを引き継がないために
ブラザーペナルティは、多くの女性が経験してきた深刻な問題でありながら、長い間見過ごされてきました。しかし近年、ブラザーペナルティという言葉を介して、女性たちが自分の体験を客観視し、向き合うきっかけを得ています。
重要なのは、これが個人的な家庭の問題ではなく、社会構造に根ざした問題であることを理解することです。被害を受けた女性たちが自分を責める必要はありません。むしろ、声を上げることで社会の変化につながる可能性があります。
一人ひとりが自分の体験と向き合い、適切なサポートを受けながら回復していくこと、そして、次世代に、より平等で公正な社会を残していくこと。それこそが、ブラザーペナルティという問題に立ち向かう最も重要な意味なのです。
あなたの経験は無駄ではありません。あなたの声は、同じ体験をした多くの女性たちの希望となり、社会を変える力となるでしょう。