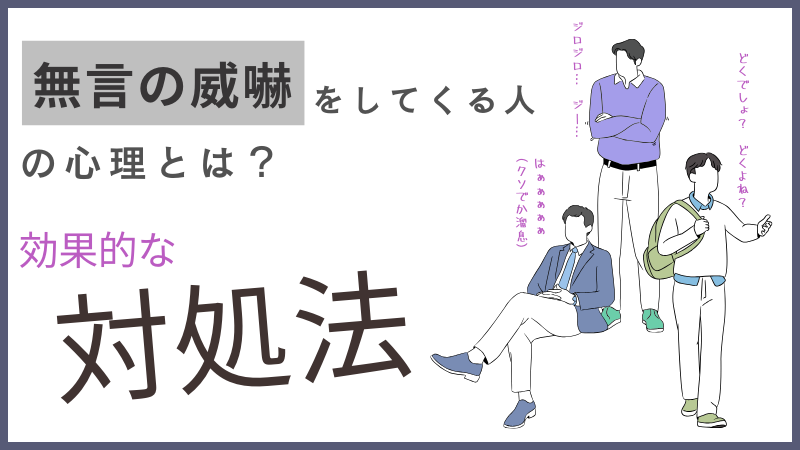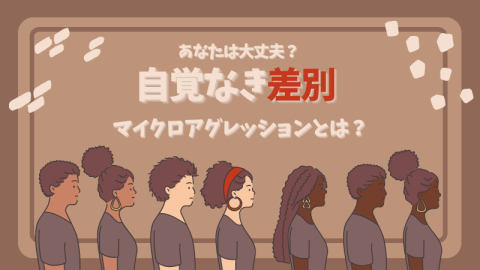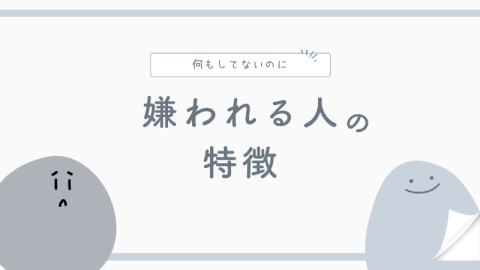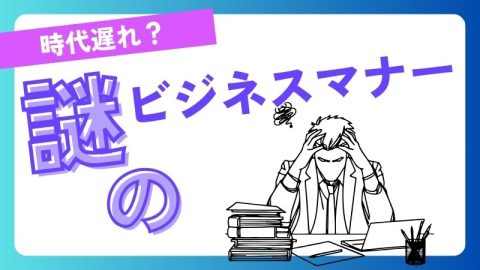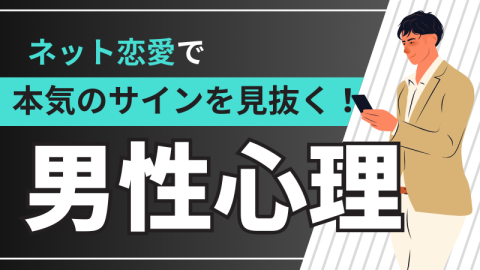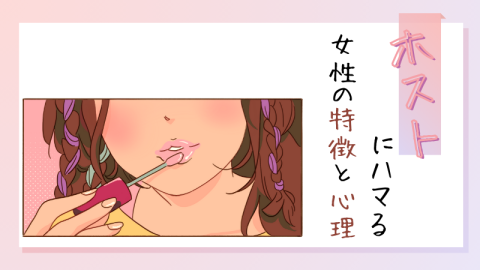駅で知らないおじさんに執拗に見られて怖かった…
職場の先輩が毎日ため息をついて圧をかけてくる…
すれ違いざまに肩をぶつけられそうになった…
このような経験はありませんか?
こうした「声なき威嚇」は明確に声に出して行われる威嚇と違って、対処法が難しいと感じている人も多いでしょう。
そこで、この記事では、言葉を使わずに威嚇してくる人の心理と、そんな状況に遭遇したときの具体的な対処法をご紹介します。
【アンケート結果】威嚇してくる人に遭遇した経験について女性約5,000人に聞いてみた
まずは女性5,252人を対象に実施したアンケート結果から見ていきましょう。
駅や電車内で「声をかけずに威嚇された」女性は約13%
| Q.駅や電車内などの公共の場で、声を掛けられずに威嚇された経験はありますか? | |
|---|---|
| ある | 685人(13.0%) |
| ない | 3,419人(65.1%) |
| どちらとも言えない | 1,148人(21.9%) |
| 総計 | 5,252人(100%) |
公共の場で無言の威嚇を受けた経験があるかを女性に尋ねたところ、13.0%(685人)が「ある」と回答しました。
一方で、「ない」と答えた人は65.1%(3,419人)、「どちらとも言えない」は21.9%(1,148人)と、経験がない人のほうが多数派ではあるものの、一定数の女性が明確に「無言の威嚇」を体感していることがわかります。
無言の威嚇、その実態とは?最多は「舌打ち・咳払い」「無言で睨まれる」
| Q.声を掛けられずに威嚇された経験がある方へ。どのように威嚇されましたか?(複数選択可) | |
|---|---|
| わざとらしい咳払いや舌打ち | 389件 |
| 無言で睨まれる | 357件 |
| 大きなため息 | 176件 |
| 足音を強く鳴らす・足踏みをする | 132件 |
| 鞄や上着などで音を立てる | 55件 |
| うめき声を出す | 74件 |
| 指を鳴らす | 14件 |
| その他 | 96件 |
無言の威嚇を受けたと答えた女性685人に、その具体的な内容を尋ねたところ、もっとも多かったのは「わざとらしい咳払いや舌打ち」(389件)と「無言で睨まれる」(357件)でした。
咳払いや舌打ちといった音による牽制や、目による無言の圧力が中心であり、言葉を介さずに不快感・敵意を伝えようとする非言語的な威圧が主流であることが見えてきます。
「目撃したことがある」人は約17%
| Q.駅や電車内などの公共の場で、声を掛けずに人を威嚇している様子を目撃したことはありますか? | |
|---|---|
| ある | 900人(17.1%) |
| ない | 3,193人(60.8%) |
| どちらとも言えない | 1,159人(22.1%) |
| 総計 | 5,252人(100%) |
アンケート対象の女性5,252人のうち、約17%(900人)が、他人が威嚇されている場面を目撃したことがあると答えています。
目撃された「無言の威嚇」もやはり咳払い・睨みが多数
| Q.声を掛けずに人を威嚇している様子を目撃したことがある方へ。 どのように威嚇していましたか?(複数選択可) | |
|---|---|
| わざとらしい咳払いや舌打ち | 215件 |
| 無言で睨まれる | 211件 |
| 大きなため息 | 101件 |
| 足音を強く鳴らす・足踏みをする | 83件 |
| 鞄や上着などで音を立てる | 37件 |
| うめき声を出す | 55件 |
| 指を鳴らす | 6件 |
| その他 | 34件 |
目撃した威嚇行動についても、やはり上位は「咳払いや舌打ち」「無言で睨まれる」でした。
これは被害者の主観だけでなく、第三者から見てもそれが威嚇として認識されていることを示しています。
これらの結果から見えてくるのは、「声をかけずに行われる威嚇」は、公共の場で一定の頻度で起こっており、特に女性にとって心理的な負担となっているという現実です。
威嚇の手段としては、舌打ちや睨みといった非言語的な方法が多く、直接的な言葉以上にじわじわと圧をかけてくる特性があります。
続いては、威嚇してくる人の心理を見ていきましょう。
威嚇してくる人の事例。無言の迷惑行為・威嚇行為のパターン
まずは、どのような行為が「無言の威嚇」に当たるのか、代表的な事例を見ていきましょう。
凝視する・ジロジロ見る


電車や駅のホーム、カフェ、職場などで、長時間にわたって見つめてくる行為は迷惑行為です。
執拗に追い回す
明らかに意図的に距離を詰めてくる、あるいは後をつけてくる行動も無言の威嚇にあたります。
すれ違いざまの攻撃・威嚇行為


近年、「ぶつかりおじさん」と呼ばれる、女性を狙って故意にぶつかろうとする男性が社会問題として取り上げられています。
実際にぶつからなくても、わざと肩をかすめるように接近したり、道を譲らず真正面から歩いてくるような行動は、身体的な接触がなくとも、明確な威圧として受け取られることがあります。
ため息・舌打ち・唸り声などの音による威圧
ため息や舌打ちといった行為で不満を表現し、周囲の空気を悪化させることも、間接的な威嚇に分類されます。言葉こそ発さないものの、「あなたが気に入らない」という敵意を暗示するような振る舞いです。
過剰な監視


常に作業を見張られる、不自然に近くをうろつかれるなど、プレッシャーを感じさせる行為も威嚇行為のひとつです。
無視・意図的な排除(いわゆる「シカト」)
あいさつしても返さない、会話の輪から意図的に外すなど、存在を否定するような行為も威嚇のひとつだと言えるでしょう。
パーソナルスペースの侵害・過剰な距離の接近


必要のない場面で極端に近づいてくる、椅子を意図的に寄せてくるなどの行動も、相手のパーソナルスペースを侵害する形の威嚇です。
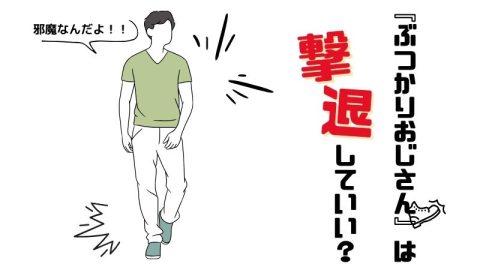
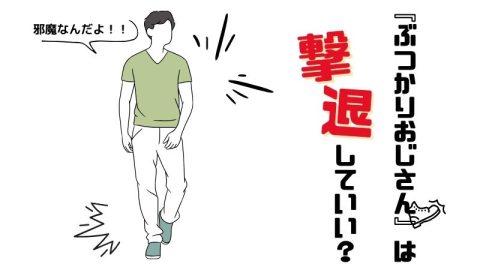
他人を威嚇する人の心理とは?
なぜ一部の人(特におじさん世代)は、このような威嚇的な行動をとるのでしょうか?
その心理的背景を理解することで、効果的な対処法や距離の取り方が見えてくるはずです。
支配欲求と優越感
自分が優位な立場にあることを確認したい、力を誇示したいという欲求から威嚇する人もいます。
男らしさや力の誇示


例えば、中年男性が若年女性に肩をぶつける仕草をして、女性が怯えて逃げていったとします。これにより中年男性は自分の力を自覚し、優越感に浸れる、というわけです。
もちろん、すべての中年男性がこういった加害行為をするわけではなく、ごく一部の人間の話ではありますが、「ぶつかりおばさん」はいないのに「ぶつかりおじさん」が多いことから鑑みるに、男性は女性よりも「自分の力を誇示したい」という欲求が強いと考えられます。
ストレス発散
仕事や家庭でのストレスや不満を、抵抗しにくいと思われる相手にぶつけている場合があります。
コミュニケーション能力の欠如
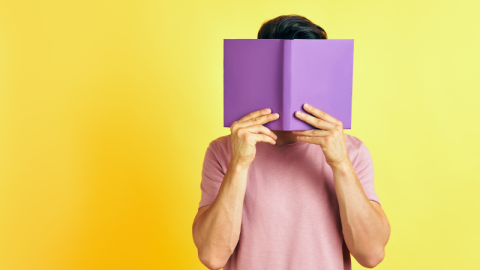
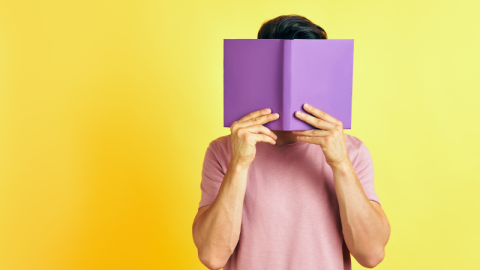
自分の不満や要求を適切な言葉で伝えられず、非言語的な方法(威圧的な態度や視線など)でしか表現できない場合もあります。
本人は「威嚇している」という自覚がないこともあるでしょう。
ジェネレーションギャップ
年配層の中には、若い世代の服装・行動・マナー・価値観に対して不満や違和感を抱く人もいます。
歪な承認欲求の表出
「自分の存在に気づいてほしい」「周囲から認められたい」といった承認欲求が、不適切な形で表れることもあります。


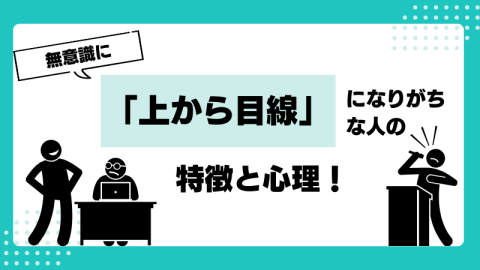
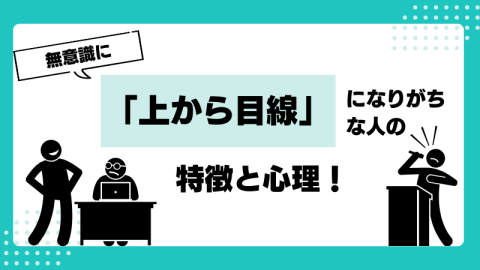


威嚇してくる人への対処法
では、実際に無言の威嚇を感じたとき、どのように対応すればいいのでしょうか?
ここでは、安全を最優先に考えた実践的な対処法をご紹介します。
安全な場所・人が多い場所に移動する


最も重要なのは自分の身の安全です。威嚇感を抱いたら、人目につく場所や店舗内、駅員室の近くなど、安全な場所に移動しましょう。
電車内なら車両を変える、道なら曲がるなど、状況を変えることで相手から距離を取りましょう。
夜道で人がいない時に誰かから威嚇された場合は、速やかに移動し、明るく人が多い場所(コンビニなど)に逃げ込んでください。
毅然とした態度を示す・過剰反応しない
可能な範囲で、背筋を伸ばし、落ち着いた姿勢を保ちましょう。過度に怯えた様子を見せると、相手に付け入る隙を与えることがあります。
とはいえ、挑発的な態度は避けるべきです。毅然としつつ、感情的な反応は抑えることが望ましい対応です。
周囲の人に助けを求める
特に危険を感じる場合は、遠慮せずに周囲の人に助けを求めましょう。
「この人が怖いので、しばらくそばにいていただけませんか?」と具体的に伝えてください。
スマホを取り出す


通話中のふりをしたり、実際に友人や家族に連絡したりすることで、「誰かとつながっている」ことを示すことは抑止効果を生む場合があります。
また、明らかに威嚇的な行為が続いている場合は、動画や音声の記録を検討してもよいでしょう。
ただし、相手と二人きりの空間で撮影を試みると、逆に相手を刺激するリスクもあるため、状況判断が求められます。
威嚇してくる人への長期的な対策
無言の威嚇や圧力に継続的にさらされるようであれば、日常の安心感を高めるための中長期的な対策も視野に入れましょう。
防犯グッズを持ち歩く


防犯ブザーや催涙スプレーなどを持ち歩くことで、緊急時の備えになるだけでなく、心理的な安心感にもつながります。
信頼できる人・専門家に相談する
不安な気持ちを一人で抱え込まず、信頼できる人に相談しましょう。特に職場での問題の場合は、上司や人事部に相談することも検討してください。
威嚇されたことでトラウマがあり、公の場所に出かけるのが怖いという場合は、医師やカウンセラーに相談しましょう。また、威嚇してくる相手が上司など職場の人間の場合、ハラスメント窓口などに相談してください。
記録をつける
被害にあった日時、場所、状況などを記録しておくと、エスカレートした場合の証拠になります。
特に同じ人から繰り返し威嚇行為を受ける場合は重要です。
護身術を学ぶ


女性向けの護身術クラスなどで基本的な身の守り方を学ぶと、実際の危機的状況での対応力が高まります。
威嚇してくる人にしてはいけないこと・避けるべき行動
次に、威嚇された時にしてはいけないことを列挙していきます。以下の行動を取ると、かえって状況を悪化させる可能性があるので注意してください。
人気のない場所で一対一で対決する
「何見てるんですか?」「こっち見るな」などと、直接言い返すことは、状況によっては相手の怒りを誘発し、エスカレートする可能性があります。
特に人気のない場所では避けたほうが無難です。
視線を合わせ続ける
威嚇してくる相手と長時間視線を合わせ続けると、挑発と受け取られる可能性があります。
チラッと見る程度にとどめ、長時間の視線の交差は避けましょう。
一人で対処しようとする
危険を感じる状況では、無理に一人で対処しようとせず、周囲の人や警備員、警察などに助けを求めましょう。
SNSでの特定・拡散は慎重に
不快な体験をSNSで拡散したくなる気持ちもあるかもしれませんが、明確な犯罪行為でない限り、個人が特定できる形での投稿は、トラブルを招く可能性があります。
法的対応が可能な威嚇行為とは?
最後に、どのような威嚇行為なら、法的に責任を問えるのか、を確認しておきましょう。
「言葉を発していない」からといって、すべての威嚇行為が罰則の対象外というわけではありません。以下のようなケースは、法的対応が可能な場合があります。
ストーカー行為
同じ人から繰り返し追従や監視を受ける場合は、ストーカー規制法の対象となる可能性があります。
暴行の一歩手前
身体的な接触がなくても、肩をぶつけそうになるなど、恐怖を与える意図のある行動は、暴行未遂や脅迫罪に問われる可能性があります。
職場でのハラスメント
無言のハラスメントも、継続的に行われれば、パワーハラスメントとして対応可能な場合があります。
「法的な罪に問えるか知りたい」という場合は、弁護士に相談してみましょう。国が運営している法テラス(※1)なら、所得制限以下の場合、無料で弁護士に相談に乗ってもらうことができます。また、犯罪行為の可能性がある場合は、速やかに警察に相談してください。
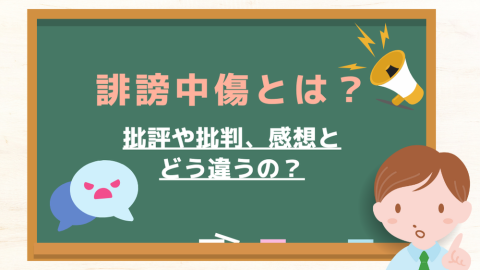
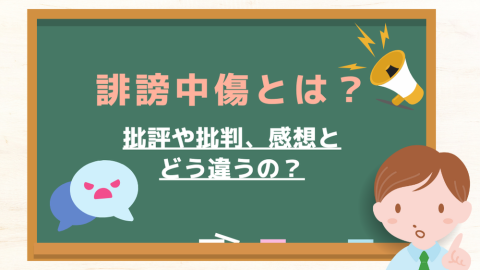
さいごに。自分を守るための「察知力」と「対応力」
無言の威嚇行為は、言葉による明確なハラスメントよりも対応が難しく、心理的負担も大きいものです。しかし、適切な対応策を知り、実践することで、不安を軽減することができます。
重要なのは、「安全を最優先すること」「必要に応じて助けを求めること」「長期的な対策も考えること」です。
社会全体の意識が変わり、このような行為がなくなることが理想ですが、それまでの間、自分自身を守るための知識と技術を身につけておきましょう。
あなたの不安や恐怖は決して「気にしすぎ」ではありません。直感を大切にし、自分の安全を第一に考えてください。そして、もし不安を感じることがあれば、遠慮なく信頼できる人や専門家に相談してくださいね。
参考
※1 法テラス
https://www.houterasu.or.jp