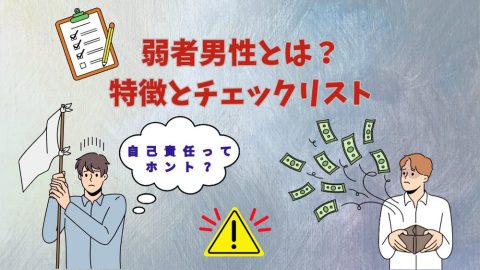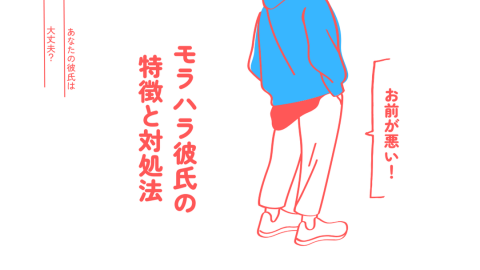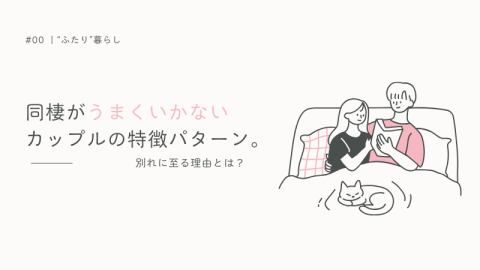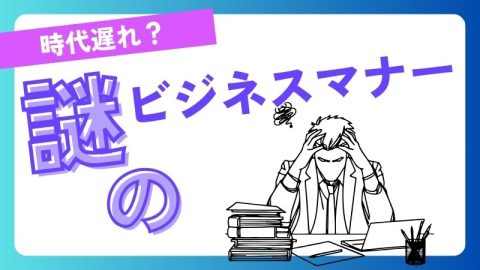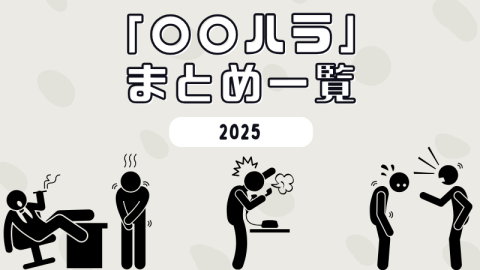近年、SNSを中心に「マンフォーギブン(Man Forgiven)」という概念が注目を集めています。
マンフォーギブンとは、英語圏で比較的最近生まれた造語であり、「男性が重大な過ちを犯しても社会から許されやすい一方、女性は同様の、あるいはより軽微な過ちでもより厳しく罰せられる現象」を指します。
なぜ、同じ罪を犯しても、男性と女性では処罰の重さが異なるのでしょうか?
今回は、マンフォーギブンの具体的事例を紹介するとともに、なぜ男性の罪は女性と比べて許されやすいのか、について解説していきます。
マンフォーギブンとは?

まずはマンフォーギブンとは何か、について詳しく見ていきましょう。
マンフォーギブン(Man Forgiven)とは、文字通り男性(Man)が許される(Forgiven)ことを意味します。
男性の犯罪や過ち、倫理に反する行為は、
- 「将来有望な男性だから」
- 「男性は女性より性欲が強いのだから」
- 「男性はいつまでも少年だから」
- 「男性はプライドの高い生き物だから」
- 「男性は家族を養わなければならないから」
- 「(男性から見て)ほんとはいいやつだから」
- 「(男性から見て)そんな犯罪をするようなやつじゃないから」
などの理由で、なかったことにされたり、処罰が軽かったりしがちです。
女性の場合、一発即退場になるようなことでも、男性の場合、何度も再起のチャンスが与えられることも少なくありません。
この現象は、深刻な性犯罪から、日常的な道徳的過ちに至るまで、あらゆる場面で観察されています。特に、権力を持つ男性や、その友人や息子など、特権階級にいる男性が犯罪を犯した際に、彼らの「将来の可能性」や「これまでの功績」が過度に考慮され、「彼らの将来がこんな些細なこと(例:強姦)で潰されるのは惜しい」などの理由で軽い処分に留まるケースが少なくないのです。
マンフォーギブンはなぜ起こる?
マンフォーギブンが起こる理由は様々です。ここでは、主な理由について解説していきます。
権力が男性に偏っている

マンフォーギブンが起こる根本的な原因は、社会の権力構造が男性に偏っていることにあります。
社会において男性が優遇されているのは、構造的な問題なのです。
司法制度、政治、企業の上層部など、重要な決定を下すポジションに男性が多く就いているため、男性の行為に対してより共感的で寛大な判断が下されやすいという現状があるのでしょう。
特に同じような背景を持つ男性同士では、「自分にも起こりうること」として加害者に同情的になりやすい傾向があります。
ホモソーシャル。男性同士の団結意識
ホモソーシャルとは、男性同士の社会的結束を指す概念です。
例えば、のちに紹介するスタンフォード大学のブロック・ターナー事件では、加害者が優秀な水泳選手であることが繰り返し強調されました。判決が軽いものだった理由は、裁判官も同じような経歴を持つ白人男性だったことが背景にあると考えられています。
裁判において、裁判官の属性(エリート男性)がシンパシーを抱きやすいのは、弱い立場にある被害者ではなく、加害者のエリート男性だ、というケースは少なくありません。
このホモソーシャル構造は、「エリート男性同士の庇い合い」として機能し、女性や他の集団に対する不利益を生み出しているのです。
女性差別・性別役割意識の根深さ

マンフォーギブンの背景には、女性に対する根深い役割意識、差別意識があります。
男性がリーダーシップを発揮した場合には「頼もしい」と言われても、女性の場合は「気が強い」「女らしくない」「でしゃばり」と言われることもあるでしょう。
こういった性別役割意識が根強いために、女性は被害に遭っても戦うことが難しくなりがちなのです。
性犯罪などに関しては、被害を訴える前に警察から「訴えたら加害者が会社を辞めさせられたり、家族が路頭に迷う、それでも訴えるのか?」と言われたり、弁護士から「性犯罪の詳細を何度も語らなければならない、あなたが傷つくだけ」と言われたりした結果、裁判まで辿り着かないケースも多々あります。
「女性は怒らない方がいい」「戦うより許す方が女らしい」
「女性ならたとえ加害者であっても男性を罰することは望まないはず」
「女性が性的なことを人前で喋るのは恥」
こういった性別役割意識・女性差別意識が女性の口を塞ぎ、加害者を野放しにすることにつながっているのです。
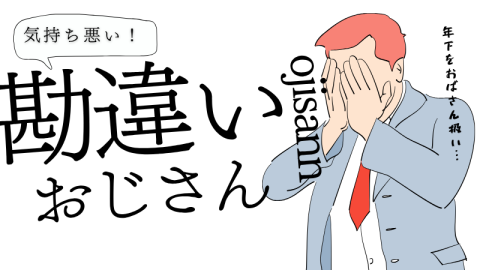

マンフォーギブンの実例。彼は将来有望だから

次に、マンフォーギブンの実例について確認していきましょう。
ブロック・ターナー事件
有名なのは、2015年にスタンフォード大学で起きたブロック・ターナーによる性的暴行事件でしょう。
検察側は禁錮6年を求刑していましたが、アーロン・パースキー裁判官が決断した量刑は、禁錮6月(うち実際に収監される期間はわずか3か月)という軽いものでした。
アーロン・パースキー裁判官は、ブロック・ターナーが「心からの後悔の念」を示していると判断し、「将来有望な若い男(プロミシング・ヤング・マン)」であることから、このような軽い判決を下したのです。
加害者の父親ダン・ターナーは裁判官宛に記した手紙において、息子が「成績が良く、誰からも好かれる」として「20年余の人生における20分間の行為に支払う代償としては厳し過ぎる」と主張したのです。
この発言は、性的暴行を「20分間の行為」と矮小化し、被害者の人生への深刻な影響を軽視するものとして大きな批判を浴びました。
さらに問題となったのは、報道の扱いです。警察は当初、逮捕時の顔写真を提供せず、報道機関は卒業アルバムの笑顔の写真を掲載したのです。通常は、逮捕時の写真が使われるはずが、白人エリート男性だから優遇されたのだ、として批判を浴びました。
アーロン・パースキーは「将来有望な若い男プロミシング・ヤング・マン」ゆえにブロック・ターナーの罪を軽くしました。アーロン・パースキーが、同じ大学に通う被害女性が「将来有望な女性」であり、その将来が潰されたことを重要視しなかったのは、加害者側に感情移入したからでしょう。
映画監督のエメラルド・ファネルは、こういった不均衡に目をつけ、医大生の女性がレイプされ、前途有望な未来を剥奪される理不尽を描いた「プロミシング・ヤング・ウーマン」という映画を作ったのです。
メディア報道の「男消し構文」。加害者ではなく被害者の写真が使われる
近年、SNS上で「男消し構文」という言葉が注目を集めています。これは、「犯罪報道において男性加害者が不可視化される現象」でありマンフォーギブンの一例です。
主要メディアの犯罪報道見出しを分析した調査によると、加害者が男性の場合は見出しに性別が記載されず、一方で加害者が女性の場合は「女」あるいは「女性」と明記される事例が認められました。
「男消し構文」の特徴
- 事件の加害者が男性の場合、見出しに性別が記載されず、○○歳従業員/知人/同級生といった表記になる。
- 加害者に関する記述そのものがなく、被害者の属性だけ強調された記載になる。
- 男性が加害者、女性が被害者の場合、被害者女性の顔写真がサムネイルに使われる。
- 男女複数人の加害者がいる際、「女ら」と女性が強調される。
- 女性が加害者の場合、卒業アルバムの写真や送検時の写真などがサムネイルになることが多い一方、男性の場合は建物の写真になることが多い。
実際の報道例として、「ミスしたら監督から『性器』を意味する言葉のセクハラ、女子サッカー元選手2人が賠償提訴」(産経新聞)や「女子大生が悲劇、看護師に襲われる…帰宅中の深夜に追いかけて押し倒し、体を触った疑い」(埼玉新聞)など、加害者が男性であることが見出しから消されている事例もあります。
「男消し構文」は、暴行・傷害・性犯罪・強盗・殺人といった暴力系犯罪で特に顕著です。これらの犯罪は加害者が男性である事例が圧倒的に多いため、男性であることを敢えて強調しない傾向もあるでしょう。
しかし、どのような理由であったとしても「男消し構文」は男性の加害行為を相対的に目立たなくさせる効果、罰を軽減する効果を持ちます。つまり、「男消し構文」は、結果としてマンフォーギブンの構造維持に一役買っているのです。
男性の不倫は許されやすい。許す女=いい女

不倫に対する社会の反応には、明確な男女差が存在しています。
近年の芸能人の不倫報道を見ると、男性よりも女性に対するバッシングの方が激しく、長期間に渡って続く傾向があることは明らかでしょう。
男性既婚者と女性独身者の不倫であっても、女性の方がバッシングされ、一気に仕事を失うことも珍しくありません。
男性の不倫の場合、「男なら性欲に負けることもある」と目され、「ダメだけど憎めないやつ」キャラで復帰が速いか、全く罰されない一方、女性の不倫は「道徳的に許されない」として厳しく糾弾され、長期間メディアから姿を消すことになりがちです。
また、男性の不倫を政治家などが行った際、「妻に怒られました」と主張する場面も多々見られます。妻が不倫に動じず鷹揚(おうよう)に構えている様子は、「いい女」だと言われたりもします。
養育費不払いの性差別など、法律が男性の罪を許す
離婚後の養育費不払い問題も、マンフォーギブンの典型例です。
厚生労働省の「令和3年度 全国ひとり親世帯等調査」によると、養育費を受け取っている母子家庭は28.1%にしか過ぎません。つまり、圧倒的多数の男性が養育費を支払っていない現状があるのです。
現時点では、養育費を払わないことは犯罪ではなく、不払いに対する刑事罰は存在しません。
公正証書に強制執行認諾文言の記載がなく、養育費を支払わずにいると、そもそも強制執行もできませんし罰則もないのです。それゆえ、子どもの貧困という深刻な社会問題を引き起こしています。
仮に女性が同様に子どもの養育の義務を果たさなかった場合、社会的な非難はより厳しいものになることが予想されるでしょう。女性がワンオペ育児に苦しんだ結果、育児放棄した場合は苛烈なバッシングが寄せられる一方、多くの男性は育児をしていないどころか、養育費すら出していないのに、その罪を問われることすらないのです。
香川照之の性加害問題とドラマ復帰
2022年8月に週刊新潮で報じられた俳優・香川照之の性加害疑惑も、マンフォーギブンの典型例です。
2019年7月、香川照之は東京・銀座のクラブで、ホステスの髪の毛をつかんだり、キスをしたり、胸を触ったり、ブラジャーをはぎ取って数人で弄んでいたとされる性加害行為が報告されました。
この報道により、香川はTBS系情報番組「THE TIME」の降板や、NHK Eテレの教養番組「香川照之の昆虫すごいぜ!」の放送中止、出演CMからの降板など、一時的にメディアから姿を消しました。
しかし、2024年にはWOWOWドラマ「災」で3年ぶりに連続ドラマ復帰することが発表されたのです。
地上波では難しくても、WOWOWドラマで復帰できるのは何故でしょうか?
それは、WOWOWにお金を払っているメインの層が中高年男性であり、香川照之の罪を軽視、あるいは許しているからです。
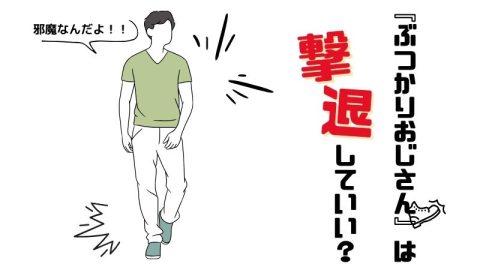
マンフォーギブンという女性差別をなくすには?

最後に、マンフォーギブンをなくすためにできることについて見ていきましょう。
マンフォーギブンについて知る
まず重要なのは、マンフォーギブンが個人の問題ではなく、社会構造の問題であることを認識することです。
法制度の改革
法制度の改革も必要です。
養育費不払いに対する実効性のある制裁措置の導入、性犯罪に対する適切な処罰の確保、職場でのハラスメント対策の強化など、法制度レベルでの改革が求められます。
そのためには、政治家・法律家の男女比を平等にすることが必要です。現状、政治家の女性比率は非常に低く、また、裁判官の女性の割合は2割程度です。マイノリティの意見が反映されるには最低3割が必要だと言われていますから、まだまだ足りていないのが現状でしょう。
メディアの役割。男性の加害を透明化しない

報道における男女の扱いの格差を是正し、客観的で公正な報道を心がけることも重要でしょう。
特に犯罪報道においては、加害者の性別や社会的地位に関係なく、事実に基づいた報道を行うべきです。
差別をしない、されない教育の充実
幼少期からの男女平等教育、メディアリテラシー教育、人権教育の充実により、性別による偏見や差別意識を解消していく必要があります。
差別をしない、また、差別をされた時にそれが差別だと気がつけるためには、継続的な教育が不可欠でしょう。

マンフォーギブンという「男性の罪を軽視・透明化する構造」にNOと言える私たちへ
マンフォーギブンは、男性中心社会の構造的問題を浮き彫りにする概念です。
単なる個人の道徳的問題ではなく、長年にわたって築かれてきた権力構造、ホモソーシャル、そして根深い性差別意識に根ざしている問題だと言えるでしょう。
「プロミシング・ヤング・マン」と同等に「プロミシング・ヤング・ウーマン」の未来が守られるために、まずは「男性の罪を軽視・透明化する構造」にNOを突きつける必要がありそうです。