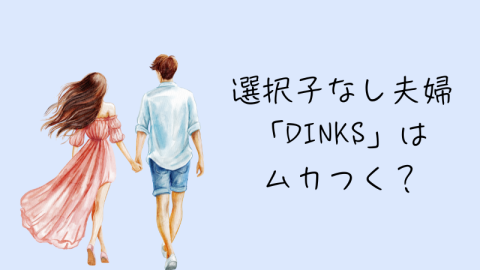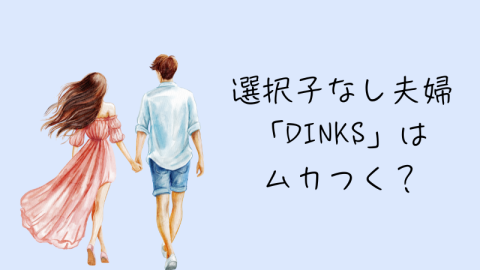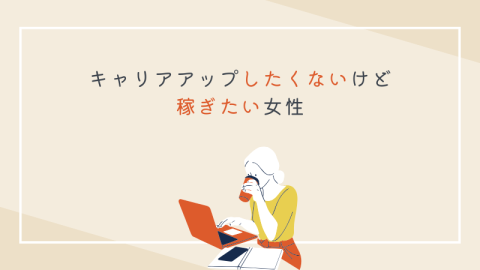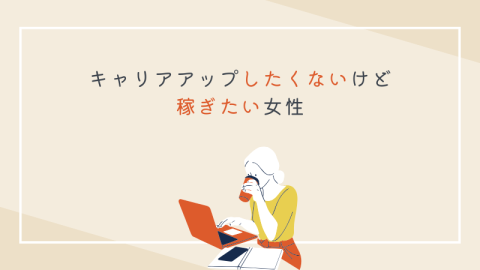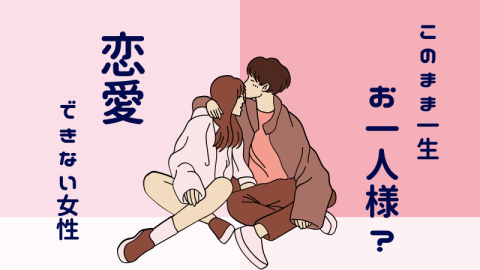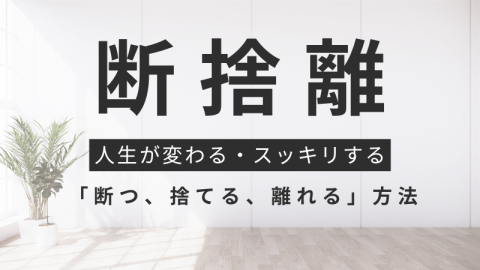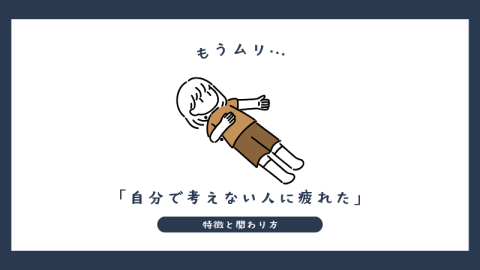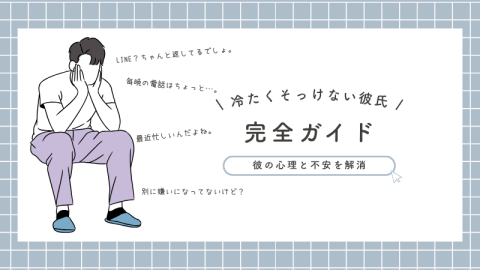数年前まで、街中の若い女性に声をかけ料理をさせたうえで、できない様を見て笑い者にする、というテレビ番組が放送されていました。
なぜ、女性が料理下手なのが面白いとされていたのかというと、
「女性なら料理くらいできる」という「女らしさ」の規範から逸脱していたからです。
現在この番組は放送されていませんが、同様の「女らしくなさ」を嘲笑う構造の番組は他にもいくつか見受けられます。
多様な生き方が認められつつある現代ですが、いまだに「女には女らしさを」「男には男らしさを」と求める社会的な価値観は消え去っていないのです。
日常生活で、女らしさや、男らしさを求められて、困った経験がある人もいるでしょう。
しかし、そもそも「女らしさ」「男らしさ」とは何でしょうか?
今回は、「女らしさ」「男らしさ」とは何か、「らしさ」を押し付けられた事例や、「らしさ」から自由になるためにはどうしたらいいのか、などを解説していきます。
「女らしさ」「男らしさ」とは何か

「女らしさ」「男らしさ」とは、女性、または男性に期待される性質、行動を指します。
日本社会で一般的な「女らしさ」「男らしさ」のイメージ
一般的な「女らしさ」「男らしさ」とは以下のような性質・行動でしょう。
「女らしさ」のイメージ
- 優しい
- 家庭的
- サポートしてくれる
- 控えめ、でしゃばらない、わきまえている
- 清楚
- 競争を好まず、和を尊ぶ
「男らしさ」のイメージ
- 勇敢
- リーダーシップがある
- 堂々としている
- 積極的
- 競争心がある
つまり、「男らしさ」はリーダー役割、「女らしさ」はサポーター役割、だと言い換えられます。
(家父長制下では)女は与える、男は受け取る

哲学者のケイト・マンは『ひれふせ、女たち ミソジニーの論理』(慶應義塾大学出版会)において、アメリカの社会で「女らしさ」「男らしさ」という役割は、家父長制に則って作られており、「女が与え、男が受け取る」という図式に当てはめることができると言います。
女性が与えるべき、とされているもの
注意、愛情、賞賛、同情、セックス、子ども(つまりは、人づきあい、家事、生殖、そして感情に関する労働)、加えて安息所、養育、安全、安心、快適などの混合的財。
男性の取り分、とされているもの
権力、威信、公的認知、位階、名声、メンツ、尊敬、金銭、およびそのほかの形式の富、階層的地位、上方への可動性、等級の高い女性の忠誠、愛、献身などを所有することで付与されることになる地位。
女らしさとは「与えること」、男らしさとは「受け取ること」という性別役割は、あまりに男性に都合が良いのでは?と思われるかもしれません。
しかし、そもそもが、家父長制下で形成された「女らしさ」「男らしさ」という概念は男性優位社会に都合のいい規範ですから、男性に利益がもたらされる(そして男性に都合よく振る舞うことで女性が利益を得る)のは、至極当然の帰結だと言えるでしょう。
「女性らしさ」「男性らしさ」は生物学的な性差に基づいているわけではない

「女らしさ」「男らしさ」の概念は、文化や歴史的背景によって形成されてきた社会的な規範であり、生物学的な性差に基づいているわけではありません。
「女らしさ」が女に自然に備わっている能力ならば、女は生まれながらに女らしいはずです。しかし、現実には、「女らしくしなさい」と言われることがあります。つまり、「女らしさ」は後から獲得し、学習する物だと言えるでしょう。
文化によっては、「女らしさ」がリーダーシップや勇敢さを含む場合もあり、日本の規範とは異なることもあるのです。
「女らしさ」「男らしさ」は強いられるパフォーマンス

ボーヴォワールの有名な言葉に「人は女に生まれるのではない。女になるのだ」という言葉があります。
哲学者のジュディス・バトラーは、「女らしさ」「男らしさ」が「パフォーマンス」であると述べています。
このように、ジェンダーが本質ではなくパフォーマンスであることを述べた理論を「ジェンダー・パフォーマティヴィティ」と言います。
ジェンダー・パフォーマティヴィティとは?
一般的に、女の子が女の子らしく育つのは、女の子に生まれたからだ、と思われています。しかし、「ジェンダー・パフォーマティヴィティ(英語:gender performativity)」はそうではない、と言い切ります。
「ジェンダー・パフォーマティヴィティ」においては、生来の本質が外に現れているのだと思われがちな「女らしさ」「男らしさ」は、実はパフォーマンスの反復によって作られて、作られたことによって「本来備わっていた性質なのだ」と事後的に思われる、と言うのです。
例えば、女の子が股を開いて座っていると、
女の子らしくしなさい!
と怒られて股を閉じるとします。その女の子が股を閉じて座っていると、
やっぱり女の子は女の子らしいね
と言われます。このようにして「女らしい女」が作られていくというわけです。
注意しなければならないのは「女になる」「パフォーマンスする」という言葉から、「私たちは自分で女らしさを選択して演じている」と誤解しがちな点です。ジュディス・バトラーはむしろ、「女らしさ」「男らしさ」は「強いられるもの」であると述べています。
「女らしくない女」はなぜ嫌悪されるのか。ミソジニー(女性蔑視)との関連


女らしく振る舞わない女性が、嫌悪され、攻撃される場面は多々あります。
なぜ、女らしくない女性は時にバッシングの対象になるのでしょうか?
それは、この社会にミソジニー(女性蔑視)が残っているからです。ミソジニーとは、しばしば全ての女性を蔑視することだと思われていますが、そうではありません。
ミソジニーは「女性が女性らしい役割を守っているときは褒め称え、役割から外れた場合は蔑視する」ことを指します。
ミソジニーが蔓延している社会においては、「女らしさ」は褒め称えられます。
甲子園に出場する男性選手を応援するために100個のおにぎりを握る女子高校生や、「主人」をサポートするために芸能界を退き家庭に収まった女性が褒め称えられるのは、「女らしさ」を体現しているからです。
一方、「女なのに」政治家として「声高に」主張する女性政治家や、「子供を産みたくない」と明言する女性は、女性役割から逸脱しているため、「でしゃばり」「わがまま」と言われることがあるのです。
ケイト・マンは、
とし、「注意深く、愛らしいしもべ」という役割から逸脱した女性はミソジニー社会ではバッシングされる、と述べています。
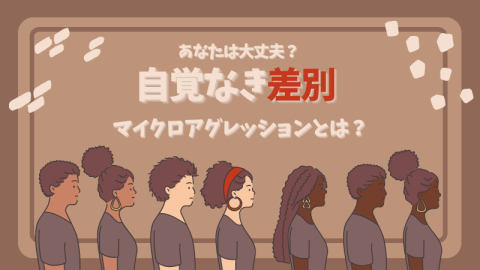
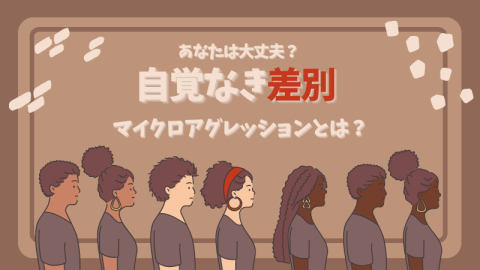
ジェンダー差別「◯◯らしさの押し付け」事例
女らしさの押し付けはあらゆる場面で見られます。
ここでは、女らしさの押し付けの事例を一部紹介します。
女性は着飾るべきだとされる。職場でのヒールや化粧の強要
職場や学校で女性にだけスカートの着用を義務付けたり、ヒールのある靴を履くことを求めたりすることがあります。また、「化粧はマナー」だとして、女性だけに着飾り労働を求める職場も珍しくありません。
大手広告代理店勤務で、過重労働とパワハラが原因で亡くなった女性社員のSNSには、女性にだけ化粧や身だしなみの基準が高く設けられていることに対する憤りが綴られていました。化粧が仕事の一部なのだとしたら、毎日女性は、30分程度の無償労働を強いられている、と見ることもできるでしょう。
しかし、こういった風潮は少しずつ変わりつつあります。
2019年には、女性だけにヒール靴を着用することを問題視した「#KuToo」というムーブメントが広がり、女性の服装規定の見直しを求める声が高まりました。
これに伴い、大手航空会社で女性のヒール着用規定が撤廃されるなど、新しい動きが広まっています。
家事・育児などのケア労働は女性の方が向いている、と言われる


家事・育児などのケア労働は女性の仕事、という固定観念は根強く残っています。
そのため、男性が自分の子どもを育てているだけなのに「いいパパ」「イクメン」などともてはやされる一方、女性はして当然だとみなされることも多いのです。
実際、統計上、夫婦が共働きであっても、家事・育児の時間は女性の方が何倍も長いのです。日本の男性は先進国のほかの国の男性にくらべて、家事・育児時間が短いことでも知られています。
これは、性別役割意識が強固であることに加え、正社員として働く場合の長時間労働が一因と言えるでしょう。
笑顔でいることが求められる
女性は、穏やかかつ笑顔であることが求められがちです。
そのため、女性が主張すると、ヒステリック、生意気、と非難されることがあるのです。一方、男性が同じことをしてもリーダーシップがある、熱い男、と賞賛されるケースもあります。
このように、男女で同じことをしているのに、性別によって受け取り方が異なることは珍しくありません。
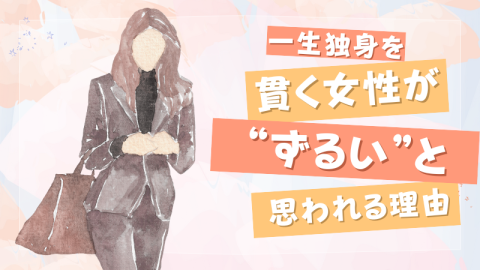
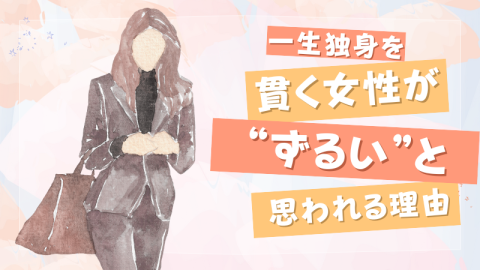
ジェンダーステレオタイプが押し付ける「らしさ」の強要がもたらす影響
こうした規範は、女性に不当なストレスやプレッシャーを与えるだけでなく、個人の自由な選択を阻む要因となります。
「女らしさ」に縛られることで、自分の本来の性格や才能を発揮できない女性も多くいます。また「らしさ」の期待は男性にも影響を及ぼします。「男らしさ」を求められる男性は、感情表現を抑圧されがちです。
「女らしさ」「男らしさ」から自由になるためにできることは?
最後に、「女らしさ」や「男らしさ」の押し付けに対する対抗策について、見ていきましょう。
「女らしさ」「男らしさ」を求める人となるべく関わらない
「女らしさ」「男らしさ」を求める人とは、なるべく距離を取り、関わらない、というのも一案です。
ジェンダーに関係なくロールモデルを見つける
性別に関係なく自分らしく生きている人を見つけて、お手本にしてみましょう。
小さなところから!制度改革に参加する


前述の「#KuToo」ムーブメントのように、働きかけることで、女らしさの呪縛を撃退していくことは可能です。
「女らしさ」「男らしさ」の成り立ちを考えてみる
自分の中に、「女・男らしくしなくては」という気持ちがあり、葛藤しているのなら、性別役割がどのように生まれたのか、を勉強してみるのもいいでしょう。
例えば、『性差の日本史』(インターナショナル新書)では、明治時代に、性別役割が意図的に強化されていった歴史を知ることができます。
「女らしいね」は褒め言葉?
「女らしいね」は一般的に褒め言葉だと言われています。また、女らしさを自ら求める女性もたくさんいます。その方が利益を得られる場面も少なくないでしょう。
一方、「女らしいね」が苦手な女性も少なくありません。
「らしさ」を推奨する社会構造に目を向ければ、「女らしいね」という言葉が女性を抑圧、従属させる意味合いを含んでいることに気がつくはずです。
女性は女らしく生きるべきなのでしょうか?
普遍的な正解はなく、各自が答えを導き出す必要がありそうです。
※参考文献
『ひれふせ、女たち ミソジニーの論理』(慶應義塾大学出版会)
『バトラー入門』(ちくま新書)
『性差の日本史』(インターナショナル新書)