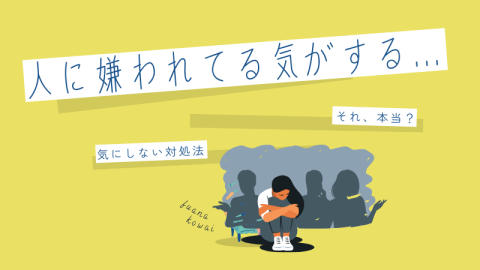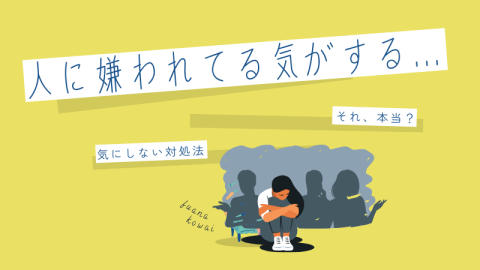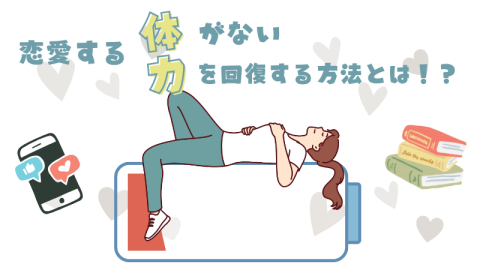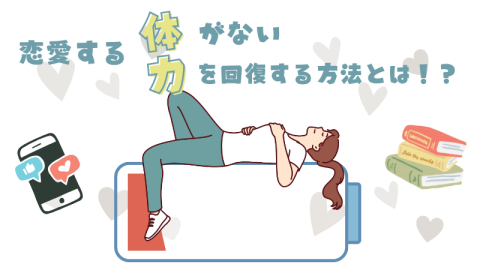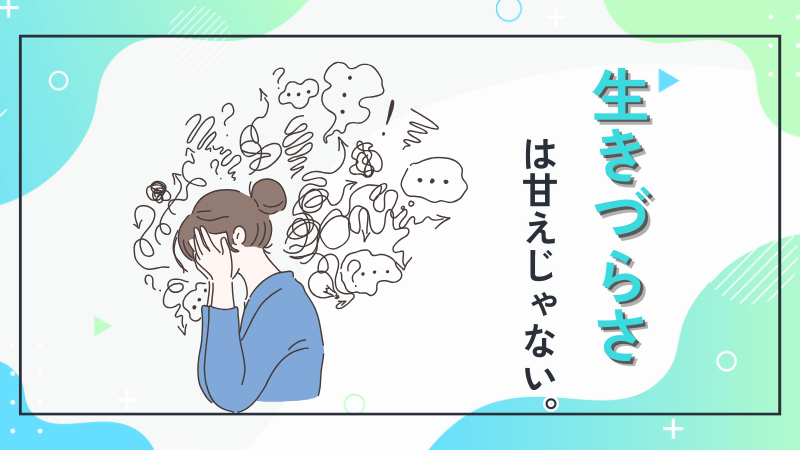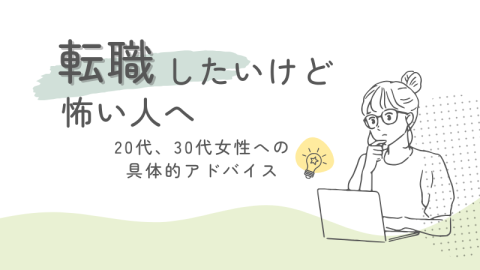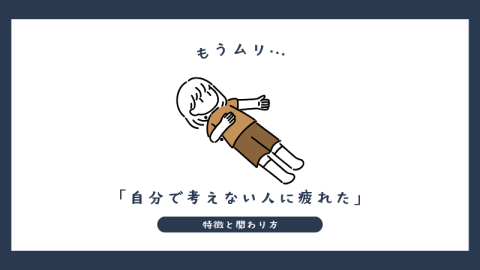「なんだか生きづらい」「毎日がしんどい」
——そんなふうに感じることはありませんか?
もしかすると、「自分が弱いだけ」「甘えているのかもしれない」と思ってしまうこともあるかもしれません。でも、生きづらいと感じるのは決して甘えではなく、多くの人が抱える悩みのひとつです。
この世界には、誰にとっても生きやすいとは言えない環境や価値観があり、その中で無理をしながら生きている人も少なくありません。生きづらいと感じる理由は人それぞれですが、その背景には、性格や考え方の傾向、そして社会の仕組みが大きく関係していることもあります。
この記事では、生きづらいと感じやすい人の特徴や原因を紐解きながら、少しでも心が軽くなるヒントをお届けします。
原因を知ることで、生きづらさが和らぐかもしれません。ひとりで抱え込まず、「こんなふうに感じるのは自分だけじゃないんだ」と思えるきっかけになれば幸いです。
【なぜ】生きづらい理由とは?生きづらさの種類と原因
「生きづらさ」とは、日常生活の中で強いストレスや困難を感じる状態を指します。
生きづらさには様々な形があり、その原因も人によって異なります。多くの場合、いくつもの要因が絡み合い、複雑に影響を及ぼしていることが特徴です。
ここでは、生きづらいケースの一例を紹介します。
心理的・精神的な生きづらさ

心の状態や特性によって、日々生きづらいと感じることがあります。たとえば、過度のストレスや将来への不安、孤独などは、生きづらいと感じる大きな要因のひとつです。
また、同じ環境にいても生きづらさを感じる人と感じない人がいることを考えると、ネガティブな思考の癖や自己評価の低さも、生きづらさに影響を与えている可能性があります。
発達障害や不安障害などの特性がある場合、
社会の中で周囲との違いに悩んだり、対人関係に強いストレスを感じたりすることがあります。人とのコミュニケーションに工夫が必要だったり、環境に適応するために常に気を張っていたりすると、心が休まる時間が少なくなり、生きづらさを感じやすくなるでしょう。
また、HSP(Highly Sensitive Person)のように、
生まれつき感受性が強く、外部からの刺激に敏感な人は、人混みや騒音、ちょっとした人間関係の変化にも影響を受けやすく、日々の生活の中で消耗しやすい傾向があります。頭の中が言葉や感情であふれ、常に情報を処理し続けてしまい、心が休まらないと感じることもあるでしょう。
さらに、うつ病やパニック障害などの精神的な疾患を抱えている場合、
気分の落ち込みや不安から外出が難しくなったり、強い孤独感や希死念慮を抱えてしまったりすることもあります。こうした状態が続くと、日常生活そのものが大きな負担になり、「生きること」自体が苦しく感じられることもあるのです。
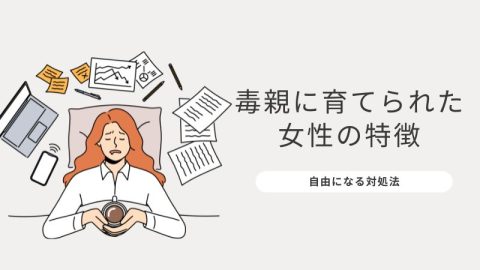
社会的な生きづらさ

家庭環境や社会のプレッシャー、偏見や差別などが原因で生きづらさを感じることもあります。
人間は社会的な生き物であるため、たとえ家に引きこもっていたとしても、世間の価値観や期待、無言の圧力を感じることは少なくありません。
また、学校や職場では、仲間外れやいじめ、パワハラやセクハラといった人間関係のトラブルに直面することもあります。しかし、こうした問題に対して声を上げることが難しく、我慢を強いられるケースも多いのが現実です。
さらに、性差別、人種差別、障がい者差別など、さまざまな形の差別が生きづらさを生む要因となります。近年では、外見に基づく偏見であるルッキズムや、年齢による差別であるエイジズムも社会問題として注目されています。
日本のように移民が比較的少ない国では、外国にルーツを持つ人が目立ちやすく、表立った差別がなくても無意識の偏見(マイクロアグレッション)を受けることがあります。
たとえば、「珍しいから」と黒人の髪を勝手に触る行為などは、その一例です。本人に悪気がないため、指摘しづらく、被害を受けた側がストレスを溜め込んでしまいやすいという問題があります。
このように、いじめや無意識の差別、職場のハラスメント、社会からの見えない圧力など、社会的な要因によって生きづらいと感じる人は決して少なくありません。
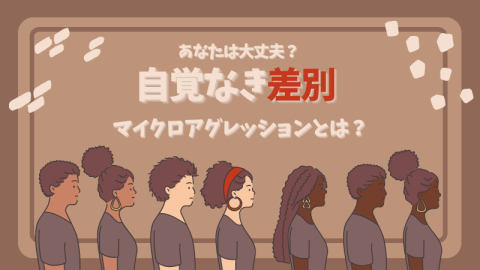
経済的な生きづらさ

経済的な困窮は、人々の心に大きな不安をもたらし、生活に余裕をなくしてしまいます。
非正規雇用の不安定な収入や、低賃金が原因で将来に対する不安を抱え、生きづらいと感じる人は少なくありません。
「来年はどうなっているのだろう」「契約が更新されないかもしれない」「給与が上がる見込みがない」「物価が高くて、食べたいものも自由に買えない」「一生懸命働いているのに、生活が楽にならない」
——こうした悩みを抱える人は年々増えているといわれています。
また、日本は男女の賃金格差が大きい国のひとつであり、シングルマザーの貧困率が高いことでも知られています。性別による賃金格差の影響で、同じ仕事をしていても女性の給与が男性より低いケースが多く、離婚後や未婚で子どもを育てる場合、約半数が貧困ライン以下の生活を強いられているのは、否定できない現状でしょう。
経済的な安定が得られない状況は、日々の生活だけでなく、将来への希望や安心感を奪い、生きづらさをさらに深刻なものにしてしまうのです。
肉体的な生きづらさ

慢性的な病気や障がい、加齢による健康問題などが、生きづらいと感じる原因となることもあります。
日本は世界でも平均寿命の高い国であり、国民皆保険制度があるため、病気になった際に医療を受けやすい環境が整っています。
しかし、長生きできることと健康でいられることは別の問題です。老化による身体の衰えや慢性的な不調によって、日常生活が制限され、生きづらいと感じる人も少なくありません。
また、生まれつきの病気や障がいを持つ人が感じる生きづらさもあります。現在の社会は、いわゆる健常者を基準に作られており、バリアフリーが不十分な場所では、ちょっとした段差ひとつでも移動の自由を奪われてしまうことがあります。
さらに、情報へのアクセスの格差も課題のひとつで、2023年に芥川賞を受賞した市川沙央さんは、著書『ハンチバック』の中で、重度の障がいを持つ人にとって「紙の本」を読むことが困難な場合が多いことを指摘しました。
電子書籍やオーディオブック(オーディブル)の普及によって、「読書のバリアフリー」が進めば、多くの人にとって情報へのアクセスが広がる可能性があります。
また、多くの生きづらさは、ひとつの要因だけでなく、複数の問題が絡み合っています。
たとえば、持病のためにフルタイムで働けず、収入が不安定になり、経済的な生きづらさにも直面している人もいるでしょう。このように、多くの人がさまざまな生きづらさの要因を同時に抱えているのです。
「生きづらい」「人生が辛い」と感じるのは甘え?
生きづらいと感じる人の中には、
同じ状況でも楽しそうに生きている人がいるのだから、自分は甘えているだけかもしれない
と思い込んでしまうことがあります。
ですが、生きづらさを感じることは決して甘えではありません。現代社会で生きるほとんどの人は、多様なストレスや困難に直面しています。そのため、誰もが一度は生きづらいと感じたことがあるはずです。
また、生きづらさの原因は、個人だけでなく社会の仕組みにあることも少なくありません。社会のシステムが変わることで、生きづらさが軽減されたり、解消されたりするケースも多いのです。
大切なのは、生きづらいという人の声を単なる甘えと決めつけるのではなく、その背景を丁寧に見つめ、個人だけでなく社会全体で適切に向き合うことです。
身近な人に相談する、行政のサポートを活用する、専門家のカウンセリングを受けるなど、必要に応じて適切なサポートを求めましょう。場合によっては、精神科やメンタルクリニックなどの医療機関を受診することも選択肢の一つです。
生きづらいと感じやすい人の性格・特徴
「生きづらさ」は社会の仕組みが大きな要因となることが多いですが、同じ環境にいても、それを強く感じる人とそうでない人がいます。その違いには、性格や考え方の傾向が影響していることもあります。
ここでは、「生きづらい」「人生が辛い」と感じやすい人の特徴を紹介します。
自己評価が低い


自分に自信がなく、常に他人と比べてしまう人は、生きづらいと感じやすい傾向があります。
完璧主義・頑張りすぎてしまう
少しのミスも許せない完璧主義の人は、自分自身に厳しくなりすぎることで、生きづらいと感じやすくなります。
コミュニケーションが苦手


人付き合いが苦手で、うまく人間関係を築けない人は、学校や職場などの集団生活の中で孤立しやすくなります。
周りに合わせすぎる・我慢強い
自分の気持ちよりも他人を優先してしまいがちな人も、生きづらいと感じやすい傾向があります。
「嫌われたくない」「波風を立てたくない」という思いから、自分の本音を押し殺し、相手に合わせすぎてしまうと、次第に心がすり減ってしまいます。
繊細で感受性が豊か・共感力が高い


感受性が豊かで、些細なことでも深く感じ取ってしまう人は、刺激の多い現代社会の中で生きづらいと感じやすい傾向があります。
また、共感力が高い人は、周囲の感情に敏感で、相手の気持ちをまるで自分のことのように受け止めてしまうため、感情を消耗したりストレスを抱えやすい傾向にあります。




どうしたらいい?生きづらい人が解消するためのヒント
生きづらさを解消するためには、以下の方法が効果的です。
- 「生きづらさ」は社会問題であることを理解し、自分を責めない。
- 自分の長所や短所、ストレスの原因を理解する。
- 定期的な運動や趣味など、ストレスを軽減する方法を見つける。
- 友人や家族、同僚と話を聞いてもらう。同じ境遇の人を探してみるのも◎。
- 達成可能な目標を決め、少しずつ前進することで自己肯定感を高める。
目まぐるしい時代を生きるわたしたち──「生きづらい」は誰もが抱える感情
「生きづらさ」は、多くの人が一度は感じたことのある、ごく自然な感情です。
それは決して甘えではなく、多くの場合、環境や社会の仕組みによって生じるもの。しかし、性格や考え方の傾向によって、生きづらさを感じやすい人と、そうでない人がいるのも事実です。
大切なのは、その悩みを一人で抱え込まず、自分の気持ちに寄り添うこと。無理をしすぎず、時には周囲の人や専門家を頼ることも必要です。生きづらさを感じる自分を責めるのではなく、「どうすれば少しでも楽になれるか」を考え、できることから一歩ずつ行動してみましょう。
また、自分自身や周りの人の生きづらさを理解し、支え合うことで、誰もが「生きやすい社会」をつくることができます。お互いを思いやる気持ちを大切にしながら、少しずつでも前に進んでいきましょう。