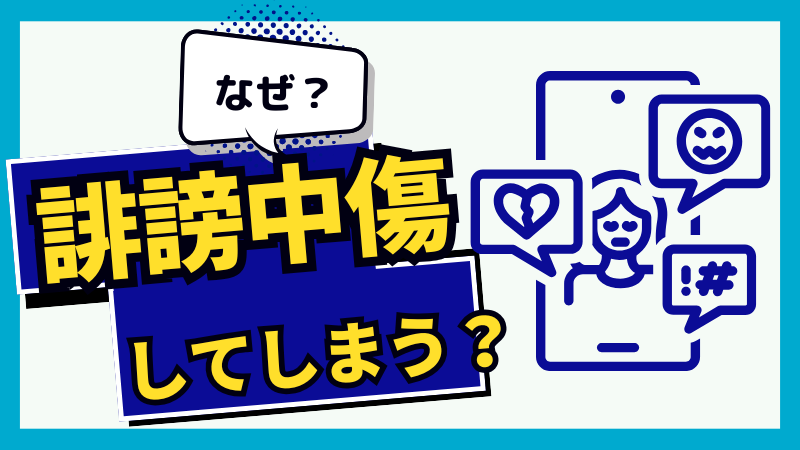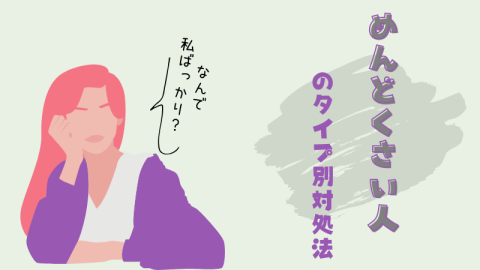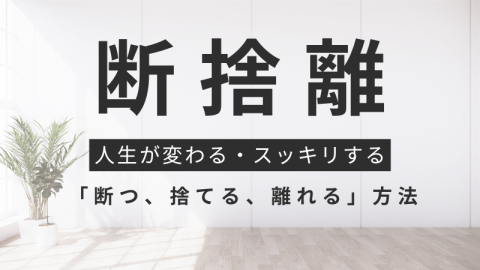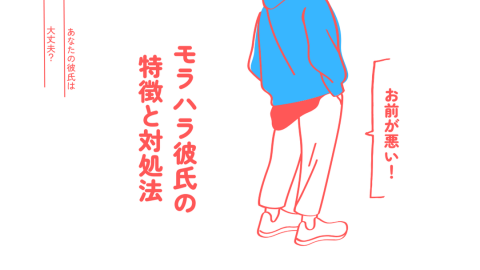X(旧Twitter)などSNSや、YouTubeのコメント欄、匿名の掲示板を見ていると、時に心が痛むような誹謗中傷を目にすることがあります。
自分に向けられたものでなくても、誹謗中傷や悪口を見ているだけで気分が落ち込んでしまうこともあるでしょう。
なぜ人は、匿名の場で他者を傷つける言葉を発してしまうのでしょうか?どういう心理が働いているのでしょうか?
今回は誹謗中傷の裏にある心理に焦点を当てます。無意識のうちに働く心理や、環境による影響を解説しつつ、自分の心を守るための対処方法を解説します。
★SNSにまつわるトラブルのひとつ、SNS疲れについては、こちらの記事で解説しています。

誹謗中傷する人の心理・言い分とは?
まずは、SNSやネット上で誹謗中傷をする人の心理について見ていきましょう。
「ずるい…!」嫉妬心

「あの人、なんであんなに幸せそうなの?」「どうして私じゃなくてあの人が…」。
自分より幸せそう、成功している、自信に満ちた人を見ると、つい比較してしまうのが人間です。人間は社会的な生き物ですから、周囲の人と比べてしまうのは致し方ないことでしょう。
比較した結果、自分には届かない輝きを持つ人に対し、無意識のうちに否定的な感情が湧き上がることがあります。これが誹謗中傷の原動力の一つなのです。
承認欲求・マウンティング心理
人を批判することで注目を集め、自分の存在をアピールしたいという欲求は誰にでもあります。
特にSNSでは「いいね」や「リツイート」という形で即座に反応が返ってくるため、承認欲求を満たすための手段として誹謗中傷が選ばれることがあるのです。
また、誰かを中傷したり蔑んだりすることで、自分が上の立場に立ったかのような優越感を味わう人もいます。
自分と違うものを受け入れる度量がない


多様性が尊重される現代社会ですが、実際には「自分と違う」ものを受け入れるのは難しいものです。
ストレス発散・匿名だから何を言っても大丈夫という心理
現代人は日々ストレスを抱えながら生きています。仕事や家庭での不満を、匿名の場で吐き出すことでスッキリしたいという心理から、誹謗中傷をする人もいるのです。
「匿名だからどうせバレない」「本当の自分じゃない」という感覚が、日常では言えない言葉を解放させてしまうのでしょう。
いくら匿名であろうとも、ネット上に書き込んだ時点で身バレのリスクはあるのですが、「匿名ならバレないはず」という思い込みが、大胆な行動をとらせているのです。
正義感が暴走


「おかしいことはおかしいと言わなければ」「誰かが言わなきゃ」という正義感から発せられる批判もあります。
例えば、「保育園落ちた、日本死ね」という書き込みがきっかけとなって、保育園不足の実態に注目が集まり、国をも動かす事態になったことは記憶に新しいでしょう。
言葉がキツくなろうとも、言わなくてはいけない批判というものは必ず存在します。特に、公の場所で発言権を持たない人の場合、インターネットで発言しなければ無視されてしまうので、死活問題だと言えるでしょう。
ハッシュタグを使ったSNSアクティビズムによって人々の生活がより良くなった事例もあります。
例えば、当時、葬儀場で働いていた石川優実さんが始めた「#Kutoo(クートゥー)」運動は、女性だけが職場などにおいてハイヒールを強制させる実態に対し、声を上げたものでした。これにより、女性だけにハイヒール着用を義務付けるのは性差別だという認識が広まり、2020年にはJALが客室乗務員にこれまで課していた3センチから6センチのヒールの着用規程を撤廃し、ヒールのない靴でも働くことが許されるようになったのです。
以上のように、世の中の不正に声をあげたことで、女性が生きやすくなった事例は多々あります。
しかし、正義感が行き過ぎると、誰かを傷つけるだけの誹謗中傷になってしまうこともあるので注意が必要でしょう。
例えば、ある政治家に対して苦言を呈するポストをしたとします。その際、政策や言葉の選び方などに対して批判するのはなんの問題もありません。
しかし、相手の容姿を揶揄するような発言をしてしまったら誹謗中傷になってしまいます。批判と誹謗中傷の線引きは時にはっきりと分けられないこともありますが、容姿を揶揄する言動が誹謗中傷であることは確かです。
【特徴】誹謗中傷ってどんな人がしてるの?中高年男性が最多
ところで、誹謗中傷はどのような人がしているのでしょうか?SNSで悪質な書き込みをしている人たちの正体についてみていきましょう。
誹謗中傷の加害者で一番多いのは50代男性


実は、誹謗中傷をするのは「特別な人」ではありません。
過去の誹謗中傷事件では、会社員、主婦、学生など様々な立場の人が加害者となったケースがあります。統計的には、50代の男性が最も多く、次に40代の男性、30代の男性、40代の女性が続きます。
しかし、だからといってそれ以外の人が加害者にならないわけではなりません。
簡単にネットにアクセスでき、匿名性を獲得できる現代だからこそ、誰もが加害者になる可能性があることを忘れてはならないでしょう。
誹謗中傷に陥りやすい状況
また、普段は穏やかな人でも環境や状況が変われば、誹謗中傷をしてしまうケースもあります。ここでは誹謗中傷をしてしまいやすい状況を列挙していきます。
- 仕事で評価されず、努力が報われないと感じているとき
- 働いているのに生活が苦しいとき
- 恋愛や人間関係で裏切られ、傷ついたとき
- パワハラやモラハラをされており、ストレスが溜まっているとき
- 睡眠不足や過重労働、体調不良によって判断力が低下しているとき
- 自分の好きなものや推しが批判されたと感じたとき
- 寂しいとき
誹謗中傷に陥りやすい性格の特徴
次に、誹謗中傷の加害者になりやすい性格の傾向について見ていきましょう。
- 完璧主義で自分にも他人にも厳しい
- 白黒つけないと気が済まない二元論的指向の持ち主
- プライドが高く、自分の間違いを認められない
- 他者への共感力が乏しい
- 自己肯定感が低く、他人を下げることで、自分を上げようとする
- 「自分はこんなものではない」「何者かになりたい」意識が強い
- 強いコンプレックスを抱えている
- 「有害な男らしさ」に囚われている
なぜ誹謗中傷はなくならないのか?
これまでX(旧Twitter)などSNSやネットの掲示板では、加害者と被害者の心理が交錯し、企業が風評被害に遭ったり、悪質な悪口が原因となるトラブルが数多く発生してきました。
しかし、なぜ誹謗中傷がなくならないのでしょうか?
ここからは、ネット上での悪質な投稿や悪口、仕返しなどの心理面における特徴が、誹謗中傷がなくならない理由にどのように関与しているかを解説していきます。
人間の本能


誹謗中傷の根底には、人間が本来持っている感情があります。承認欲求、優越感を得たい欲求、嫉妬心、怒り、不安……これらはどんな人にも存在するものです。
集団心理が影響している
一人では考えもしないことでも、集団でワイワイしているうちに、極端な方向に進んでしまうことを表した心理学の用語で「集団極性化」というものがあります。
ネット上で「集団極性化」が発生し、一人では到底考えもつかなかった過激な誹謗中傷をしてしまうこともあるのです。
ネットリテラシーの浸透不足
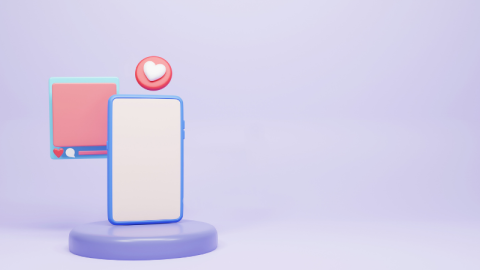
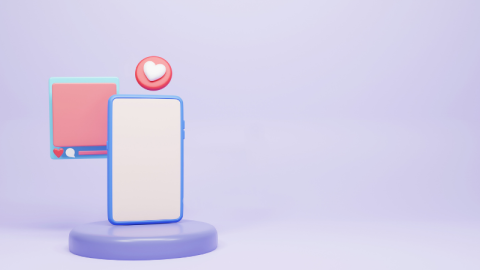
インターネットやSNSが日常に溶け込んだ現代ですが、適切な使い方や影響力についての教育は十分とは言えません。
罪に問われにくい
匿名性が高い、手軽に発信できる、一度の投稿が瞬時に拡散する……こういったインターネットの特性はすべて、誹謗中傷をしやすくしています。
また、文字だけのコミュニケーションは相手の反応が見えないため、言葉の重みを感じにくいという点も重要でしょう。誹謗中傷された相手は深い心の傷を受け、最悪の場合、自殺してしまうケースもあります。言葉が人を殺すのです。
しかし、多数の誹謗中傷が殺到していた場合、「実際に誰が殺したのか」は不透明です。
現在は、ネット上で誹謗中傷をされた際、被害者が自分で弁護士を雇うなりして、時間とお金をかけて、加害者を突き止める必要があります。多くの場合、疲弊してしまい、行動を起こせません。
誹謗中傷をした個人がすぐに特定され、責任を取らされる社会であれば、これほどまでに多くの誹謗中傷が行われてないはずです。
誹謗中傷から自分を守るための対策
最後に、誹謗中傷から自分を守るためにはどうしたら良いでしょうか?対策のヒントを確認しておきましょう。
情報は受け身でなく能動的に取りに行く
SNSのアルゴリズムは、私たちの興味や反応に基づいて情報を表示します。しかし「おすすめ」に表示される情報は、必ずしも自分にとって必要なものとは限りません。
エコーチェンバーにも気をつけましょう。
エコーチェンバーとは、自分の興味のある投稿を見たり、いいねを押したりしているうちに、カスタマイズされた情報ばかり見てしまう現象のことです。
例えば、陰謀論を信じている人は、陰謀論関連の投稿ばかりを見て、いいねを押します。
そうすると、陰謀論がまさしく全員が興味を持っているトピックであり、正しいことなのだと信じ込んでしまうのです。
情報が正しいか否かに関わらず、SNSを使っている人は誰しも、「いつのまかに極端に偏った情報」ばかりを見続けることになりがちです。
こういった事態を避けるためにも、一つのSNSだけから情報を得るのではなく、幅広い情報収集を心がける必要がありそうです。
自分の時間を大切に


結局のところ、ネット上の他人の誹謗中傷を見る時間は、あなたの人生にとって価値のある時間でしょうか?
現在は「注意経済(アテンション・エコノミー)」の時代であり、人々の注意や関心が経済的な利益を生みます。
例えば、あなたがSNSに長く滞在すればするほど、プラットフォームの提供側は広告を配信しやすくなり、儲かります。
つまり、誹謗中傷を眺めたり、投稿したりしている時間は、プラットフォームの利益のためにあなたの人生が搾取されている時間だ、と言い換えることもできるでしょう。
誹謗中傷に注意を奪われている時間を、自分の成長や幸せにつながる活動に使えば、心はもっと豊かになるはずです。
コメント欄を見ない
ネットでニュースや動画を見るとき、本編だけを見て、コメント欄はスルーする習慣をつけましょう。
SNSの機能を活用する
各SNSには、不快な内容から自分を守るための機能が備わっています。
Xの場合
- 特定のワードをミュートする
- 特定のアカウントをブロック、またはミュートする。
- 返信を制限する:設定から、返信できる人を限定することができます。
Instagramの場合
- 非表示の単語を設定する:設定から特定のワードを含むコメントを自動的に非表示にできます。
- 「興味なし」機能を活用する:探索タブの投稿を長押しして「興味なし」を選択することで、類似コンテンツが表示されにくくなります。
- コメントを制限する:設定から、コメントできる人を限定できます。
YouTubeの場合
- 「興味なし」機能を使う:おすすめ動画の「…」から「興味なし」を選択できます。
- 履歴の一時停止をする:アカウント→履歴とプライバシー→YouTube履歴から、視聴履歴を一時停止することで、関連動画の精度を下げることができます。これにより、エコーチェンバーを緩和することができるでしょう。
- 特定のチャンネルをブロックする:チャンネル名の横にある「…」から「このチャンネルをおすすめに表示しない」を選択できます。
自分の時間と心を守るためにも、誹謗中傷と距離を置こう


スマホにSNSが入っているということは、手の中にパチンコ台を持っていることと同義です。「次は何か面白い情報に出会えるかも」という期待感が、SNS依存を引き起こすのです。
開発者は、「どうやってユーザーを依存させるのか」を考え、アプリを設計しています。
私たちの時間とアテンション(注意)が、アプリやプラットフォームの提供者の経済的利益のために狙われていることを自覚するべきでしょう。プラットフォーマーは誹謗中傷を規制しようとしません。なぜなら、誹謗中傷でSNSが盛り上がり、人々がよりSNSに依存すれば、金が儲かるからです。
また、誹謗中傷した加害者が糾弾され、罰を受けることになったとしても、プラットフォーマーは責任を問われません。誹謗中傷をした責任を問われるのは、加害者本人だけなのです。
プラットフォーマーは誹謗中傷された被害者も放置します。それどころか、誹謗中傷さえも経済的利益に変えてしまうのです。誰かが誰かの誹謗中傷加害者となり、リスクを負って承認欲求を満たしたり、被害者となり心に深い傷を受けたりしている間、ノーリスクで利益を得ているのはプラットフォーマーだけだと言えるでしょう。
プラットフォーマーはあなたの心を守ってくれませんし、責任も取ってくれません。ですから、自分で自分の時間と心を守る必要があります。
ネットの世界は広大で、そこには素敵な出会いや発見がたくさん待っています。
同時に、使い方によっては、無為に時間を奪われ、搾取されてしまう可能性があることも理解しておかなければならないでしょう。




参考
※1 神戸新聞NEXT 誹謗中傷の加害者は50代男性が最多
https://www.kobe-np.co.jp/rentoku/omoshiro/202203/0015132768.shtml