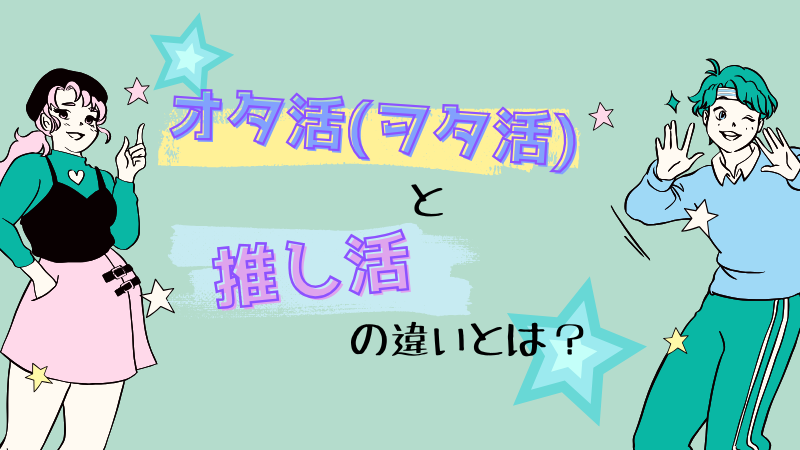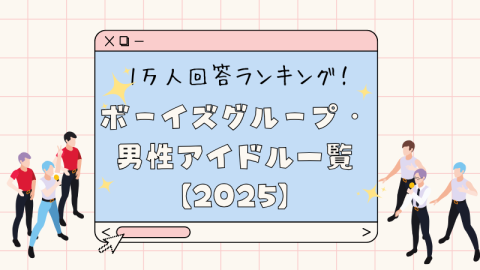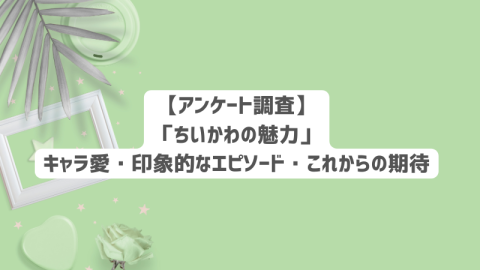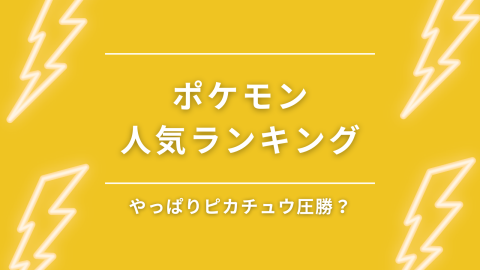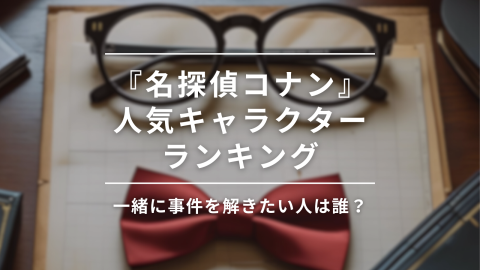近年、「オタ活」や「推し活」という言葉を耳にする機会が増えています。
オタクという言葉は、かつてマイナスイメージが強い言葉でしたが、「電車男」などオタクをプラスに表現するコンテンツが増えて以降、ポジティブに捉える人が増えています。
また、特定の人やキャラクターを推すことに対して、以前は「お金の無駄」「気持ち悪い」と言われることが多かったのに対し、今では「推し」がいることは珍しくなくなり、広く受け入れられるようになりました。
ただ、両者の違いについて、明確に説明できる人は意外と少ないかもしれません。実際に、オタ活と推し活は似ているようでいて、楽しみ方や目的にはそれぞれ異なる点があるのです。
今回は、オタ活と推し活の違いを事例とともに解説。活動の違いや、具体的な種類についても紹介していきます。
オタ活(ヲタ活)って何?定義・事例

「オタ活(ヲタ活)」とは「オタク活動(ヲタク活動)」の略称で、自分が熱中している趣味に関する活動全般を指します。
オタ活の対象は、アニメ、漫画、アイドル、鉄道、ミリタリー、盆栽、2.5次元の舞台など多岐にわたります。単にコンテンツを楽しむだけでなく、創作活動に発展することも珍しくありません。
また、「オタク」と「ヲタク」は基本的に同じ意味ですが、ニュアンスや使われ方に違いがあります。
オタ活(ヲタ活)の事例
- コレクション(フィギュア、グッズ、限定版など)を集める
- イベント(コミケ、文学フリマ、ゲーム大会、フェスなど)に参加する
- ファン同士で考察や議論を楽しむ
- 創作活動(同人誌制作、イラスト、コスプレなど)をする
- 作品の歴史や制作背景について調べる
- オフ会やファンミーティングに参加する
推し活って何?定義・事例

推し活とは、推し(応援したい人やグループ、キャラクター)を積極的に応援する活動を指します。
推しの対象は、人気のメジャーアイドルや地下アイドル、俳優、声優、アーティスト、キャラクター、VTuberなど多岐にわたり、オタ活と比べて「個」に焦点が当てられている点が特徴です。
また、オタ活は自分が趣味を極めることに焦点が置かれている一方、推し活は、「推すこと」つまり、「応援すること」に焦点が置かれている点でも違いがあります。
本当にその活動が推しのためになっているのかどうかは活動内容によりますが、少なくとも推し活を行なっている本人は「推しのためになるような応援の仕方をしよう」と心がけていることが共通点といえるでしょう。
推し活の事例
- CDやグッズを購入し、売上に貢献する
- サバイバル番組に出場している推しに投票する
- ライブやイベントに参加し、直接応援していることを伝える
- 推しの魅力をSNSやブログで発信する
- 推しのMVなどの閲覧回数を増やすため、何度も再生する
- 聖地巡礼(推しが訪れた場所や作品の舞台に行く)をする
- 推しが関わる商品(広告商品やコラボグッズなど)を購入する
- 推しの情報を常にチェックし、新たな活動を応援する
- スーパーチャット(投げ銭)で応援する
- クラウドファンディングに参加する
- 推しの誕生日を祝うためにファンイベントを企画する
- 推しの私物と同じものを購入し、愛用する
- 推しのファンを増やすために周囲の人に宣伝(布教)する
タイプ別の種類
推し活は、現代のポップカルチャー(大衆文化)を語るうえで欠かせない要素です。
規模がどんどん大きくなり一大産業になった結果、推しを推す方法は多岐にわたっています。ここでは、近年よくある推し活の種類を解説していきます。
視聴・鑑賞型

推しが出ているドラマやアニメを繰り返しみたり、DVDを購入して何度も鑑賞したりするのは、推し活の基本でしょう。
グッズ収集型
推しのアクスタやぬいぐるみ、トレーディングカード、シール、うちわなど、グッズを購入し、収集している人もたくさんいます。そういったグッズを部屋に飾り、推しに囲まれた暮らしを送っている人も珍しくありません。
イベント参戦型・直接接触型

ライブ、コンサート、舞台、握手会、お話会、ファンミーティングなどに参加することで生の推しを見ることに生きがいを感じている人もいます。
課金型
クラウドファンディングに参加したり、スーパーチャットを送ったりして、推しに課金することを楽しんでいる人もいます。SNS以前は、推しに直接投げ銭し、推しから「ありがとう」といってもらうなんて、考えられないことでした。
現在は、ファンと推しの距離が身近になりがちであり、それゆえ、推し活への熱狂ぶりも高まっていったのでしょう。
聖地巡礼型

ドラマの撮影場所になったロケ地に出向いたり、推しの通っていたカフェに行ったりする推し活もあります。
推しの実家が喫茶店などを営んでいる際には、その喫茶店に行くことで推し活をする人もいます。
ファン同士の語り合い型
ファン同士のコミュニティに参加し、情報交換をしたり、推しの尊さについて語り合ったりする形の推し活もあります。
ファン同士が繋がって、生誕祭などのイベント時に大きなお花やケーキを送るケースもあるようです。
布教型
推しを応援するために、CDを配るなどして布教活動を行う人もいます。
また、推しを採用してくれたドラマのプロデューサーや、CMに抜擢してくれた企業に対し、「ありがとうございます!」とお礼を言う人もいます。
創作意欲爆発型
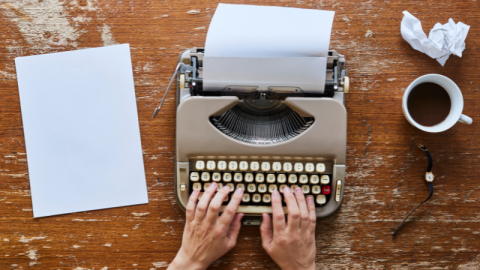
推しを主人公にした二次創作や夢小説を書くなど同人活動を行う、コンサートで使うためのうちわや横断幕を作るなど、創作活動を行う人も珍しくありません。
推し活の魅力やハマる心理、メリット・デメリットについてはこちらの記事がおすすめです↓

#オタ活(ヲタ活)と#推し活の違いとは?
これまで紹介してきた通り、オタ活と推し活はよく似ていますし、かぶっているところもあります。では実際、両者にはどのような違いがあるのでしょうか?
ここでは、オタ活と推し活の違いについて解説ていきます。
【比較】対象・活動内容の違い
| 対象の違い | 活動内容の違い | |
|---|---|---|
| オタ活 | ジャンルや作品全体 | コレクションや創作、イベント参加など |
| 推し活 | 個人やグループ | コレクションや創作、イベント参加など、オタ活と同じ活動も多い。しかし、「推し」を応援するという意図があるため、「宣伝・応援・課金」に力が入れられがち |
推し活をしている人の中には、自身のことを「オタク」だと認識している人も少なくありません。
例えば、アイドルオタクで、とあるアイドルグループのXさんを応援している田中さんという人がいたとします。田中さんが、Xさんのうちわを作ってライブに参戦するのは、オタ活でしょうか?推し活でしょうか?
田中さんはアイドルのことが好きなオタクであり、推しがいる人です。つまり、田中さんのこの活動は、オタ活であると同時に推し活でもあるわけです。
オタ活と推し活には細かい違いがありながらも、「オタ活でもあり推し活でもある」ことも多いのも、また事実でしょう。
違いはあっても、どちらも自分を大切にしながら楽しむことが大切
オタ活と推し活はどちらも「好きなものを楽しむ」活動であるという点においては共通していますが、対象や目的が少し違うということがわかりました。
オタ活はジャンルや作品全体を深く楽しむのに対し、推し活は特定の人物やキャラクターなど「推し」を応援し、支えることに重きを置いた活動です。どちらも楽しみ方に正解はなく、自分に合ったスタイルで活動するのが一番です。
気をつけなければならないのは、推し活・オタ活に熱中しすぎてしまい、生活ができなくなるレベルで時間やお金を使ってしまうことです。