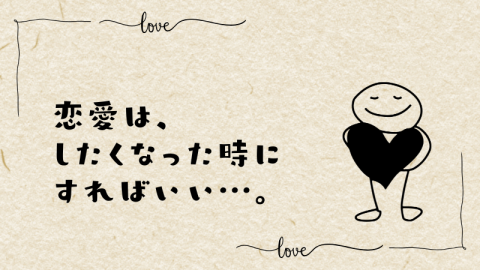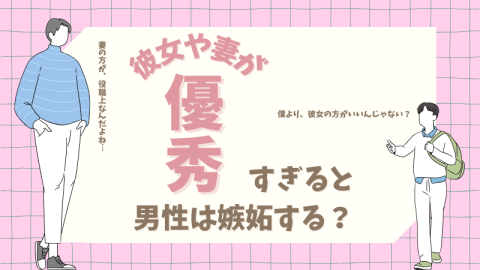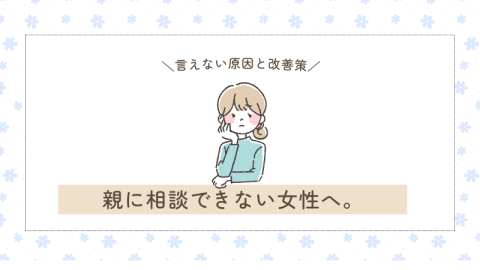#さす九という言葉をご存知ですか?
「#さす九」は、九州に根強く残る男尊女卑文化を揶揄する言葉としてSNSで使われるネットスラングです。
2024年の日本のジェンダーギャップ指数は146カ国中118位で経済、政治分野で特に男女差が大きいことが示されています。日本は先進国であるのも関わらず、男女の賃金格差が大きく、政治家は男性だらけで、女性の社会的地位が低く、男尊女卑な古い価値観が色濃く残る国だと指摘されています。
そんな日本の中でも、特に男尊女卑が根深いといわれているのが九州。近年、SNSでは「#さす九」という言葉が広まり、九州のジェンダー観に関する議論が活発になっています。
では、なぜ九州では男尊女卑が今も根強く残っているのでしょうか?
今回は、#さす九 に焦点を当て、日本、そして九州における男尊女卑文化の背景をひも解いていきます。
日本全体の男女格差の現状。男尊女卑は九州だけではない
日本は長年、男女格差が大きい国だと国際的に指摘され続けています。
世界経済フォーラム(WEF)が発表する「ジェンダー・ギャップ指数(Global Gender Gap Index)」では、2024年のランキングで146カ国中118位と、先進国の中では最低レベルに位置しています。なぜ、日本の男女格差は改善されないのでしょうか?
日本における男尊女卑の要因として、主に以下のような問題が挙げられます。
作られた伝統・家父長制

日本は長年、家父長制の社会構造を持っており、男性が一家の大黒柱として経済を支え、女性は家庭を守るという役割分担が根付いてきました。
特に戦後の高度経済成長期には、「男性は外で働き、女性は専業主婦になるべき」という考え方が一般的でした。
そのため、「日本はもともと男女の性別役割が明確な国だったのだ」と思っている人も少なくありません。しかし実際、「男性は外で働き、女性は専業主婦になるべき」という文化が作られたのは、明治政府以降です。
明治以前は、男女の性別役割は明確ではありませんでした。明治政府が「男性を家長とし、女性を“主人に支えるポジション”にする」という明確なビジョンを打ち出した結果、「日本の伝統・家父長制」が作られたのです。
明治時代の官僚、吉井友実(よしいともざね)が記した日記には、明治4年の8月11日に明治政府の方針で女官たちが全員免職されたことが記されています。吉井は、女性が権力の座から引き摺り下ろされたことを受け、「“女権”がこの日に一挙に解消され、愉快極まりない」と率直な思いを綴っています。
この日記からも明らかなように、明治以降、女性差別は加速したのであり、「昔は女性差別が激しかったけれど、今は解消に向かっている」という言説は真実ではないのです。
歴史を紐解いてみると、男女差別は一直線に解消に向かっているのではなく、いつでもアップダウンやバックラッシュがあり、将来的に現状よりも差別が苛烈になる可能性はゼロではないと言えるでしょう。
職場における男女格差「ガラスの天井・マミートラック」

日本の労働市場では、依然として女性が不利な立場に置かれる傾向があります。
女性の昇進を阻む「ガラスの天井」問題も深刻です。経済産業省のデータによれば、日本の企業の管理職に占める女性の割合はわずか14.8%(2022年)であり、国際的に見ると極端に低い水準です。
結婚や出産を経た女性が、キャリアアップの機会を失い、単純業務やパートタイム労働に追いやられる傾向も続いています。出産した女性は、「マミートラック」と呼ばれる低賃金キャリアの道に追いやられる現状も改善される見込みが立っていません。
政治分野での女性の少なさ
日本の国会議員に占める女性の割合は低く、2022年時点で衆議院の女性議員比率はわずか10%程度です。これはOECD加盟国の中でも最低レベルであり、政策決定の場で女性の意見が十分に反映されにくい状況を作り出しています。
メディアの影響
日本のメディアでは、いまだに「女性は控えめであるべき」「家庭的であるべき」「アシスタントポジションであるべき」「リーダーよりもサポーターであるべき」といったジェンダーステレオタイプが強調されることが少なくありません。
ニュース番組やバラエティ番組で、教える側やMCは中年あるいは高齢男性である一方、アシスタントは若く綺麗な女性であることが典型的です。さらに、メディア露出に関しても、男性は年齢が上がっていっても露出度が変わらないか右肩上がりになる一方、メディアに出ている女性で一番多い年齢層は20代で、30代以降の女性はどんどん露出が減っていっています。
日本における男尊女卑の具体的なエピソード例

こうした状況から、日本では日常的に女性が差別を受ける場面が少なくありません。
例えば、日本では法律上、夫婦別姓が認められておらず、結婚した女性の約96%が夫の姓に変更しています。最近の調査では、既婚女性の半数以上が「本当は名前を変えたくなかった」と回答。
夫婦がそれぞれの姓を選べる「選択的夫婦別姓制度」も議論されていますが、社会的な圧力や制度の不備により、多くの女性が不本意ながら改姓を余儀なくされているのが現状です。

X(旧Twitter)で話題の「#さす九」とは?その意味と背景
これまで見てきたように、男尊女卑は九州だけの問題ではありません。ですが、九州は日本の中でも際立って男尊女卑が目立つと指摘されています。
そんな中、SNSでよく使われるようになったのが「#さす九」という言葉。「さすが九州」の略で、九州地方に根強く残る男尊女卑的な文化や価値観を皮肉るネットスラングです。読み方は「さすきゅう」です。
特に、結婚後の夫婦関係や職場での男女格差に関するエピソードが話題になりやすく、九州から他の地域へ移住した人が語る「九州脱出成功後のカルチャーショック」も頻繁に共有されています。「九州ではまだこんなに男女格差があるのか」と驚く人が多いのも特徴です。
「#さす九」はこれまでもたびたび議論されてきましたが、福岡市に本社を置く西日本新聞がこの件についての記事を掲載したことで、さらなる波紋を呼びました。記事の中には「地域差別ではないか」「不愉快だ」との意見も紹介され、賛否両論はますます加熱しています。
#さす九 問題。九州に男尊女卑が根強いと言われる理由とは?

ところで、なぜ九州には根強く男尊女卑が残っているのでしょうか?
九州地方は、「九州男児」という言葉に象徴されるように、男性優位の文化が根付いているとされています。これは、江戸時代から続く封建的な価値観の影響が強く、家父長制が色濃く残っていたことが一因です。女性は「家を守るもの」とされ、外で働くよりも家庭を支えることを求められてきました。
九州は女性の政治参加が進みにくい環境があり、地方議会や市町村長の女性比率が全国平均よりも低いのが女性の地位が向上しない一因だと言えるでしょう。
九州の男尊女卑が強い地域はどこ?
県別のデータを見ると、熊本県では「幼い頃から九州内を転々としたが、熊本が一番男尊女卑な考えが強いところだと思う」という意見があり、性別役割分担意識が強い傾向が指摘されています。
熊本県は「男は外で働き、女は家を守るべき」という考えが根強く、女性のキャリアアップが阻まれることも多いようです。
また、宮崎県では、女性の国会議員や市町村長が不在であり、政治分野での男女格差が全国最下位となっています。
さらに、福岡県などの都市部でも、一見すると男女平等が進んでいるように見えますが、実際には職場での昇進機会や賃金格差において、依然として男女間の違いが顕著に見られます。
九州の男尊女卑に関する具体的な #さす九 エピソード
では、実際の「#さす九」エピソードを見ていきましょう。
「#さす九」エピソード1 「嫁」という労働力は、家を存続させるために存在する
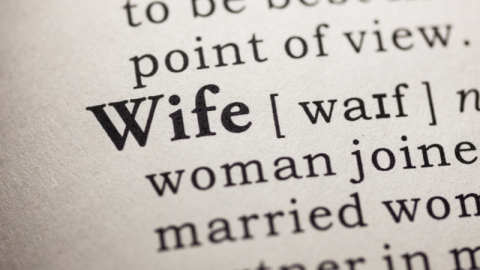
結婚後、義両親と同居することになった際、「嫁は朝5時に起きて家族の朝食を準備するのが当たり前」と言われた。拒否すると「嫁の自覚がない」と叱責された。(40代女性)
妊娠が発覚した際、「女の子は後継になれないからいらない」と言われた。(30代女性)
「#さす九」エピソード2 女性は学び&仕事のチャンスが限定されている
女の子は家庭に入るのだから大学まで行く必要はないと言われた。弟は大学に進学していた。(50代女性)
職場で男性社員は外回りの営業を任されるが、女性社員は事務職に固定される傾向があり、昇進の機会が限られていると感じた。(20代女性)
飲み会で男性社員が「九州の女は家庭的でなきゃ」と発言し、それを批判した女性が職場で冷遇されるようになった。(30代女性)
会社の採用面接で「結婚や出産の予定は?」と聞かれ、女性のキャリア継続が難しい環境がいまだに残っていることを実感した。(20代女性)
このように、九州では伝統的な価値観が根強く残り、それが女性の社会進出を妨げる要因の一つとなっています。
興味がある方は、X(旧Twitter)で「#さす九」のハッシュタグを検索すると、さまざまなエピソードがまとめられている投稿が見つかるので、チェックしてみてください。
九州地方の男尊女卑の風潮は変化していく?
近年、一部ではジェンダー平等への意識が高まっており、「九州男児」という言葉に対する評価も変化しています。
調査によれば、50歳以上の男性は「九州男児」にポジティブな印象を持つ一方、若い世代や女性はネガティブな印象を持つ傾向があります。
また、九州地方でも男女共同参画の推進や、性別役割分担意識の解消に向けた取り組みが進められています。
例えば、福岡市では女性起業家を支援するプログラムが充実しており、女性が独立してビジネスを立ち上げる環境が整いつつあります。熊本県では、育児休業の取得を促進するための企業向け支援制度が導入され、男性の育休取得率を向上させる取り組みが行われています。
このように、九州の男尊女卑的な文化はまだ残っているものの、時代とともに少しずつ変化していることがわかります。
さいごに。男女平等に向けて、一人ひとりの意識改革が必要
しかし、近年は社会全体でジェンダー平等への意識が高まり、政策や企業の取り組みによって少しずつ改善が進んでいます。もちろん、このまま一直線に男女平等が進んでいくとは考えづらいでしょう。紆余曲折やバックラッシュがあるはずです。
今より男女差別が激しい方向に向かう可能性もありますから、そうならないために、一人ひとりの意識改革が求められるでしょう。
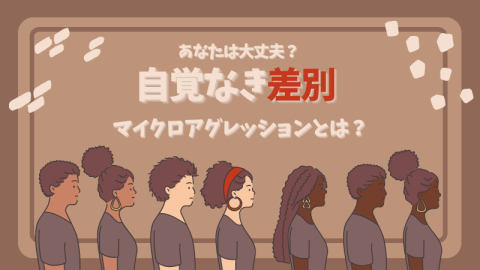
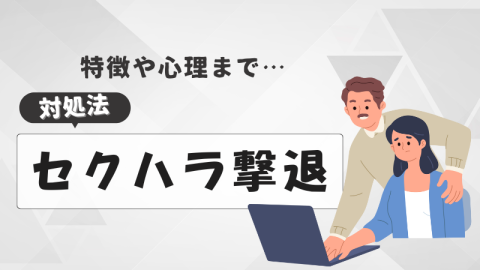
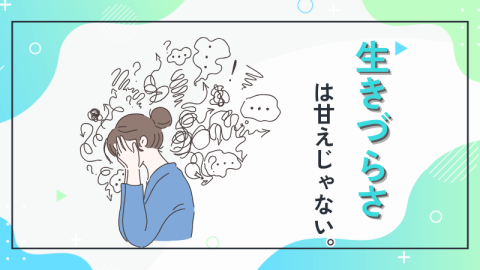
参照
朝日新聞 九州男児の実際、知りたい
https://www.asahi.com/articles/ASQ1Q6DZ1Q1PTIPE01L.html
Think都城 ジェンダーギャップの現在地
https://think-miyakonojo.jp/article/4117/
法政大学 地域における男女共同参画が進まない理由
https://www.parti.jp/festa/data/w1_udai%28chiiki%29.pdf
南日本新聞 九州男児の評価は何点?
https://373news.com/_news/storyid/166266/
佐賀県 男尊女卑について
https://www.pref.saga.lg.jp/kiji003106875/index.html
男女共同参画局 男女共同参画に関する国際的な指数
https://www.gender.go.jp/international/int_syogaikoku/int_shihyo/index.html