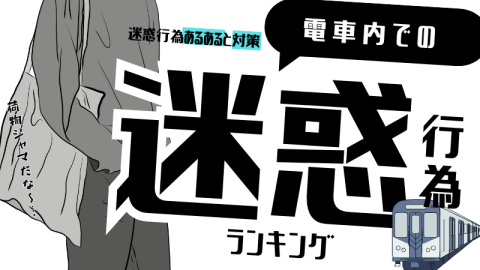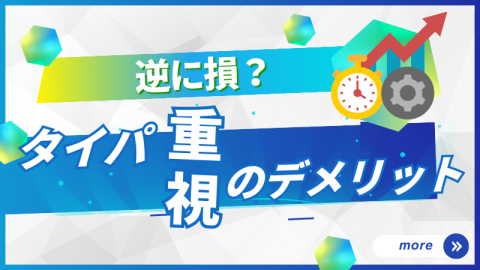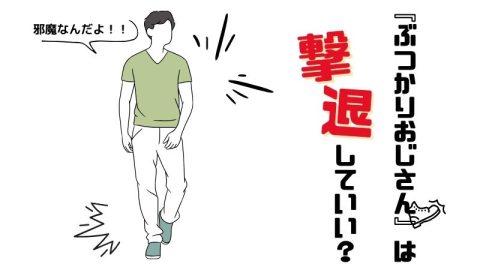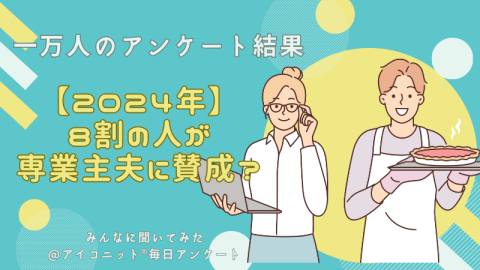加齢はどんな人にでも平等に訪れる現象ですが、「年相応」であることを望んでいる人は少ないようです。
その証拠に、
「◯歳なんですか、見えない!」「若いですね」
は褒め言葉だと認識されている一方、
「42歳なんですか?それくらいだと思いました!」
「わ〜年相応ですね!」
と言う人は存在しません。
実年齢よりも若く見られるためにアンチエイジングに励んだり、筋トレしたりする人は男女問わず存在しますが、年齢に対するプレッシャーは女性の方が大きいようです。
一昔前は、「女性に年齢を聞くのは失礼」などと言われていましたし、まだ20代なのにも関わらず、「もうおばさんだから」と自虐する人も珍しくありません。
なぜ、女性はこんなに加齢に対して敏感なのでしょうか?
なぜ、「年を取りたくない」「若さ=価値が高い」と思い込みがちなのでしょうか?
多くの女性が抱える「加齢が怖いと感じる気持ち」「年齢への不安」。それは単なる老化への恐怖ではなく、もっと深いところで私たちの心を支配している「呪い」なのかもしれません。
今回は、日本に蔓延る若さ至上主義という呪いを解く方法について解説していきます。
「年を取りたくない」「加齢が怖い」心理の背景。その不安の正体とは?


「年を取りたくない」という気持ちの奥底にあるのは、実は老いそのものへの恐怖ではありません。多くの場合、それは「若さという価値を失うこと」への恐怖です。
私たちは無意識のうちに、年齢と自分の価値を結びつけて考えるよう刷り込まれています。20代は「可能性に満ちた黄金期」、30代は「もう若くない」、40代以降は「下り坂。可能性は狭まっていく」と。
この不安の正体を因数分解すると、以下のような要素が見えてきます。
若くて可愛い女性というポジションを失う・アイデンティティの揺らぎ
これまで「若くて可愛い」という理由で得られていた注目や好意が減ることに不安を感じる人もいます。特に、外見的な魅力で評価されることに慣れてしまっている場合、その変化は大きな喪失感として受け止められるかもしれません。
実際、若くて可愛いというポジションは「なめられ」と紙一重ですから、そのポジションを脱却することで、新たなステージに行くことは可能です。しかし、これまで慣れ親しんでいたポジションを抜け出す時、未知の世界に踏み出すような不安を感じる場合もあるのです。
そのため、30代に入る時は、「これからどうなるんだろう?もう若くて可愛い女の子ポジじゃない」と不安を感じたとしても、
加齢による容姿の衰えが不安
若い頃の容姿が、加齢によって変わっていくことの不安を感じる人もいます。
特に、容姿を生かす仕事をしている人ほど、この不安は顕著です。容姿の変化が、仕事やお金や評価に直結する場合、容姿の変化は一大事でしょう。
また、そういった仕事をしていない人も、加齢による変化に不安を感じ、時に、アンチエイジングにお金を投入することになります。
時代についていけなくなる不安


中年以降の人間が「Z世代は何を考えているのだろう」など若者のトレンドを必死に知りたがるのも、時代遅れになりたくないという気持ちの表れかもしれません。
自分自身は変わっていないのに、世の中の価値観がどんどん変わっていき、これまで許されていたことが許されなくなったり、これまでダメだったことがOKになったりすることは多々あります。
価値観をアップデートできないがために、「時代遅れの人」になってしまうことに対し、不安を感じる人もいます。
新たなキャリアや恋愛、結婚、出産のチャンス…「可能性」が減る不安
若い時は可能性に満ちた時だと言われます。「これから何にでもなれる・挑戦できる」自由と時間が、若い人にはあります。年齢が上がるごとに、就職などの機会が減っていくのは残念ながら事実です。
仕事編
年齢は就職や転職において、大きな要因です。
◯歳以上は採用しない、と決めている会社はたくさんありますが、求人票にはその旨が記載されていません。なぜなら、年齢差別になってしまい、法律違反になるからです。公には表記していませんが、年齢で足切りしている企業が大多数なのです。
同じ投資をするなら、若い人に投資した方が長く働いてもらえるため、投資しがいがあると考えるのです。また、自分より年上の人を指導するのは気が引けるという理由もあるでしょう。
このような理由から、年齢が上がることで、仕事のチャンスが減っていくという現実があります。
結婚編
結婚については、現在、男女ともに初婚年齢は30前後です。
それゆえ、周囲の人が結婚してゆく30前後に「このままでいいのだろうか」と不安を感じる人は少なくありません。結婚だけなら何歳からでもできるのですが、年齢を重ねるごとに周囲には既婚者が増えていくため、可能性が狭まっていくように感じる人もいます。
また、少子化対策の流れが、国やメディアが女性の出産タイムリミットを過剰に強調し、煽る風潮もあります。
日本には「高齢出産」という言葉があります。これは、女性が35歳以上の出産を指すものですが、他の国ではほぼこういった言葉は使われていません。ヨーロッパ出身の友人にこのワードを話したところ、「女性差別的だ」と言っていて驚いていました。
実際、年齢が上がるごとに出産に対するリスクが高まるのは現実です。しかし、それを言えば、精子だって老化することが近年の研究では明らかになっています。それにも関わらず、卵子凍結は普及し始めているのに、精子凍結は全く普及していません。
なぜ、さまざまな科学的エビデンスがあるのにも関わらず、精子が老化することは、メディアでほとんど取り上げられないのでしょうか?
なぜ、女性だけが「若い時に産め」「35歳以上は高齢。ハイリスク!」と脅されているのでしょうか?それは、精子も老化するという事実を受け入れたくない男性が少なくないからでしょう。
その結果、「男性は何歳でもいつまでも妊娠させることができる。高齢であっても問題ない。でも、女性はタイムリミットがあるから急がなければ」と焦る女性が出てきています。
このように、加齢によってさまざまな可能性が狭まっていくように感じて、不安を抱く女性は少なくありません。
若いうちは可能性がありすぎるからこそ、可能性がなくなっていくことに不安を感じるのでしょう。


「若さこそ女の価値」と、自分で自分に呪いをかける女性が多いのはナゼ?


就職や出産など、加齢によって可能性が減っていくことは、事実としてあるでしょう。それとは別に、「若さこそ女の価値」という呪いが存在していることも、事実です。
「30過ぎたらババア」「女は若い方がいい」「お局様」。こうした言葉を一度でも耳にしたことがない女性は、おそらくいないでしょう。これらの言葉は、私たちの心に深く刻まれ、やがて自分自身の価値観として内在化していきます。
まさに「呪い」のように。
20代の女性が「30過ぎたら終わり」と言うとき、彼女は数年後の自分に呪いをかけているのです。「お局様」は年齢を重ねた女性が会社にいることを揶揄する女性蔑視の言葉ですが、そのことに気が付かずに、「お局がむかつく」と言う女性も珍しくありません。
なぜこのように「自分で自分に呪いをかける」女性が珍しくないのでしょうか?
男性の価値観を内面化する女性
本書によると、アメリカのエスニックマイノリティの研究において、マイノリティ集団の人々は、ホスト社会のマジョリティが持つマイノリティについてのイメージを内面化する傾向があると言います。
つまり、マジョリティから付与されるネガティブな第三者イメージは、当事者に内面化されてネガティブなセルフ・イメージになるというのです。
例えば、
白人優位社会において、黒人が「性欲が強くて、ずるがしこい人」と見做されると、黒人はそのイメージを内面化して自己否定するか、あるいは戯画的に演じるか、もしくはそれに反発してマジョリティに過剰に同一化しようとするのだといいます。
「若さこそ女の価値」という価値観は、本来女性発信のものではなかったはずです。女性を客体化し、「若い女の方がいい」と値踏みした男性の価値観です。この価値観を、女性側はいつの間にか内面化しているわけです。
上野は「あらゆる差別のうちで、第三者による差別以上に辛いのは、自己差別に違いない。なぜなら他の誰が自分を責めるより以前に、自分が自分を受け容れることができない、つまり自己否定感から逃れられないからである」と指摘しています。
若い女性を「価値ある商品」にするマスメディア・社会
同時に「女性は若い方がより商品価値がある」という価値観は単なる妄想ではないという点にも留意すべきでしょう。テレビのジェンダーバランスを調査した以下の報告書をみてください。
調査報告 テレビのジェンダーバランス
https://www.nhk.or.jp/bunken/research/domestic/pdf/20220501_7.pdf
テレビ出演者8480人を対象にした本調査によると、テレビ出演者の割合は6割が男性、4割が女性でした。
特筆すべきは、女性の出演者で一番多い年代は20代であり、30代以降、右肩下がりに減っていく一方、男性の出演者は、20代、30代、40代と右肩上がりで、もっとも多い出演者が40代だという点です。
テレビでは若い女性を積極的に登用される一方、30代以降の女性は徐々に仕事を失っていきます。
かつて、日本テレビでは30歳を過ぎた女性アナウンサーがニュース番組から降板する慣行がありました。これを性差別として勝訴したのが、田原節子(旧姓:村上)です。以降、30歳以上の女性もニュースに出られるようになりました。しかし、依然として、30以上の女性はメディア露出が減っていってしまっているのです。
この構造は、2025年に日本で放送された映画『サブスタンス』にも現れています。
主人公は年齢を重ねることで女優としてのキャリアを追われ、それゆえ若さにしがみつきます。本作では、なぜ、彼女が若さに執着し、暴走してしまったのか、その原因をこれでもかと描き切っています。本作を観た人は、彼女もまた、マジョリティの価値観を内面化したゆえに、年齢を重ねた自分を受け入れられなくなってしまった被害者であることに気がつくでしょう。
若い女性を「価値ある商品」、そうでない女性を「旬は過ぎた」とみなす広告、メディア、エンターテイメントに触れ続けていたら、女性が歳をとることに不安を感じるのも、致し方ないことです。
しかし、ここで立ち止まって考えてみてください。この呪いは、誰にとって都合が良いものなのでしょうか?
若さを失った女は「誰にとって」価値がないのか


「年を取った女性には価値がない」という考えは、果たして誰の視点から生まれているのでしょうか?
男性にとって価値がない?
確かに一部の男性は若い女性を好む傾向があります。
ところで、「若い女性にしか価値を感じない」男性からの評価を、気にする必要はあるでしょうか?「若い女性にしか価値を感じない」男性からの評価は、歳を取れば下がるのですから、遅かれ早かれ失墜します。
そんなものに一喜一憂するのは馬鹿らしいと言えるでしょう。
社会にとって価値がない?
年齢を重ねることで、社会に居場所がないと感じる人もいるかもしれません。
出産後に職場復帰しようとしたら年収が大幅に下がったとか、就活に苦労したなどの経験をする可能性もあるでしょう。病気で働けなくなったり、生産的な活動ができなくなったりするかもしれません。
社会にとって価値がないと思うような状態になってしまうケースもあるでしょう。その状態に虚しさを感じ、何か価値を提供したいのなら、ボランティア活動などで地域に貢献するという方法もあります。
また、そもそも社会というものは人のために存在しているものであって、その逆ではありません。
私って社会にとって価値がないのかも
と思い始めたら、そもそも価値を提供する必要があるのか、そこに立ちかえる必要があるでしょう。
自分にとって価値がない?
これが一番重要な問いです。
年を重ねることで、あなた自身が感じる充実感や満足感は本当に減るのでしょうか。
30代、40代になって「20代の頃より今の方が幸せ」と感じているという人もいます。年金暮らしの女性が戻りたいと思うのは、20代や30代ではなく、子育てなどが落ち着いて自由な時間ができた50代だという調査もあります。
年を重ねることで何かを「失う」ことばかりを想像し、逆に何を「得られる」かについては考えが及ばない状態になってしまうのは、もったいないことです。
人間は消費財ではありません。年齢を重ねることで失うものもあれば、得るものもあるのです。
年齢を重ねることで得られる真の価値とは?


では、年を取ることで私たちは何を得ることができるのでしょうか。
精神的に強くなる
若い頃の承認欲求や他者依存から解放され、自分軸で生きられるようになります。
若いうちはメンタルが不安定な人であっても、大人になるうちに自分の心との付き合い方を学び、精神が安定していきがちです。
「メンヘラ」イメージが若い女性ばかりだという点に注目してください。歳を重ねるごとに、自分のメンタルの操縦方法を学ぶ女性は少なくないのです。
深い人間関係が築ける
表面的な付き合いではなく、本当に心を通わせる関係を築く力が身につきます。友情、愛情、家族関係、すべてにおいて長期間関係を築くことで、深いつながりを作れるようになります。
経験値や判断力がアップする
多くの経験を積むことで、物事の本質を見抜く力が身につきます。「これは本当に大切なことなのか」「今するべきことは何か」を的確に判断できるようになるのです。
また、若いうちの失敗から学び、同じ失敗を繰り返さない、という賢さも身につけることができるでしょう。
創造性が増す
若い頃の衝動的な創造性とは違う、深みのある表現力が身につきます。人生の酸いも甘いも知った上での創作は、より多くの人の心に響くものとなるでしょう。


「若さ=価値」という呪いを解くための具体的なアイデア


次に、どうすれば「若さ=価値」という呪いから解放されることができるのか、について見ていきましょう。
ユーモアで対処する
みうらじゅんは、著書『アウト老のすすめ』(文藝春秋)で44歳の女性からの「老けていく自分が嫌で仕方ない」という読者からの相談に、以下のように答えています。
「年齢とともに変わってきた箇所を指差し、声を出して「老いるショック!」と言ってみてください。老いるショックは、あなただけじゃなく、みんなに平等にやってきます。その真理に逆らうことはできません。それに抗って、若づくりを始めるのは、老いるショックの思うツボです。
ここは周りと「若見え」を競い合うよりも、ナチュラルにしておくか、わざと老けを盛って「老けづくり」をしてみる。そうすると年齢を聞かれた時に「意外と若いんですね」と言われるかもしれません。老化はしょうがないことです。しょうがないことには、しょうもないことで対処するのが一番だと僕は思っています」
「仕方ないことにはユーモアで対処する」は一つの処世術でしょう。
世界に目を向ける
日本は特に若い女性に価値をおく国ですが、世界には様々な美しさ、価値観が存在します。
フランスでは年齢を重ねた女性の魅力が称賛され、インドでは年長女性が家族の精神的支柱として尊敬されています。多様な価値観に目を向けてみましょう。
ロールモデルを見つける
年齢を重ねても輝いている女性たちの存在に目を向けましょう。彼女たちがどのように人生を歩んできたかを学ぶことで、歳をとるのが楽しみになるかもしれません。
内面の豊かさに目を向ける
外見の変化に一喜一憂するのではなく、知識、経験、人間関係など、目に見えない資産に注目してみましょう。
元気がもらえる本・映画・ドラマなどを見る
ドキュメンタリー『アイリス・アプフェル!94歳のニューヨーカー』は90代でファッション界のアイコンとして活躍する女性アイリスにフォーカスしたものです。
このように年齢を重ねても自由にファッションを楽しんでいる女性から元気をもらえるかもしれません。
また、近年ドラマ化された『団地のふたり』(藤野千夜)などの小説を読んでみるのもいいかもしれません。50代の団地に住むふたりが、慎ましくゆったり過ごしているだけの話なのですが、地に足のついた女ふたりの友情に癒されます。
歳をとることが怖いのは、その実態がぼんやりとし過ぎているからかもしれません。未知なるものへの恐怖を和らげるために、年配の女性が活躍するコンテンツを摂取してみましょう。
加齢によって失うものと、得るものがある
最後に、一つ確実に言えることがあります。
今日のあなたは、昨日のあなたより多くの経験を積んでいます。明日のあなたは、今日のあなたよりもさらに多くのことを知っているでしょう。それは、失うことではなく、得ることなのです。
「年を取りたくない」と思うその気持ちは、とても自然で理解できるものです。しかし、その不安に支配されて今この瞬間を楽しめないのは、とてももったいないことです。
若さ至上主義という「呪い」から解放されたとき、あなたは「若々しく」ではなく、「自分らしく」生きることができるでしょう。